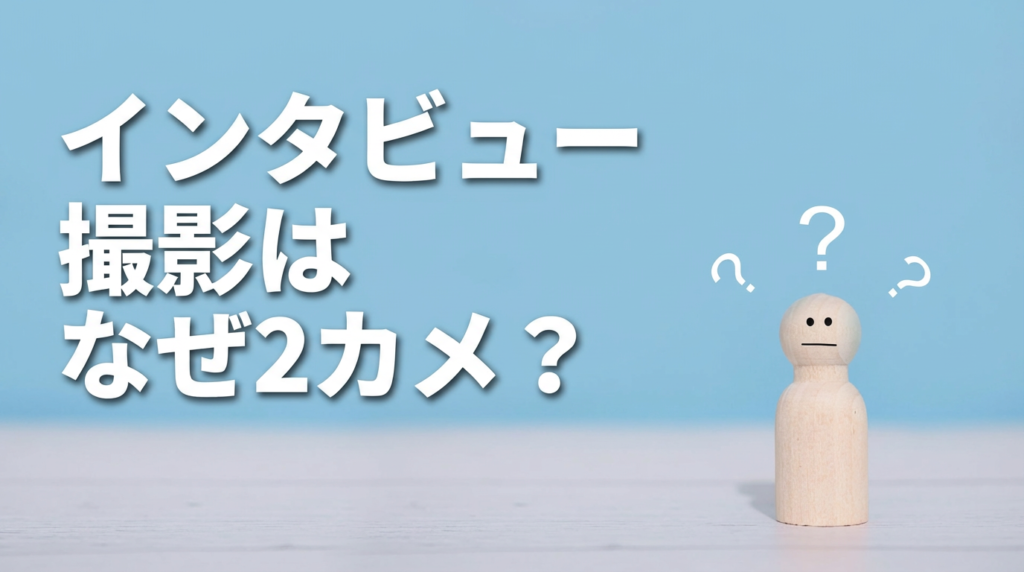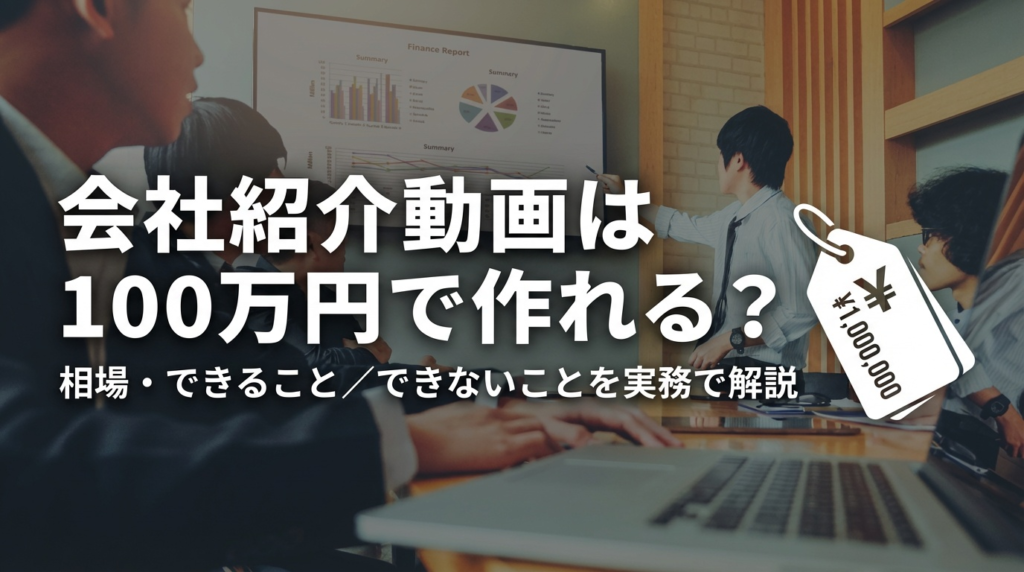動画による情報発信が多くの業界で活発になる中、製造業でも「工場そのものを見せる」というアプローチに注目が集まっています。特に、現場の雰囲気や設備・スペック、働く人々の様子などを視覚と聴覚を通じてリアルに伝えられるのが、動画の最大の強みです。
これまでの写真や文章だけでは伝えきれなかった、製造現場の臨場感、技術力、清潔さ、安全意識といった要素も、映像であれば直感的に伝えることができます。視聴者にとっては、「実際に工場を訪れたかのような没入感」を得られるため、営業・採用・広報などさまざまな場面で活用が進んでいます。
さらに、Webサイト、展示会、採用イベント、SNS、海外向け営業資料など、マルチチャネルで使いまわせるのも工場紹介動画の大きな魅力です。
本記事では、目的に応じた構成や演出の考え方を整理し、動画ならではの強みを最大限に活かすためのノウハウを解説していきます。
筆者のプロフィール
まず、この記事を読んでいただくにあたって「誰が何を書いているのか?」も非常に重要な要素になると思いますので、簡単に私のプロフィールをまとめています。

【株式会社case 代表取締役/動画制作プロデューサー:加藤智史】
新卒で入社した動画制作会社で広告・マーケティング・採用・人材研修など約400本の動画制作に携わる。その後、TVCMなどの制作を行う、大手制作会社にアカウントエグゼクティブとしてジョイン。数千万円規模のプロモーション案件に携わり、動画にとどまらないクリエイティブ制作やプロジェクトマネジメントを経験。現在は本メディアの運営を通じた企業動画の受託制作や、動画制作会社の営業支援などを行う。
動画制作会社(予算数十万円〜数百万円)での営業兼プロデューサーとしての役割を中心に、広告代理店(予算数百万円〜数千万円)でのアカウント(クライアントと社内クリエイティブチームの窓口、PM業務を担当する役割)なども経験しているため、比較的高い説得力で本記事をお届けできるのではないかと考えています。
よくあるQ&A
- 工場紹介動画の制作費はどれくらい必要?
-
制作体制や内容によって大きく変動しますが、50万円〜300万円程度で制作されることが多いです。
- 工場紹介動画の製作期間はどれくらい?
-
約2ヶ月ほどを想定しておくと、無理のないスケジュールだと言えます。
2. 工場紹介動画で実現できること(=目的・効果)
工場紹介動画は、単に製造現場を撮影するだけでは動画としての効果を発揮できません。目的に応じて構成や演出を設計し、工場の強みや技術力、生産体制を“臨場感をもって伝える”ことで、初めて有効な映像コンテンツとなります。
ここでは、工場紹介動画を活用することで得られる主なメリットをご紹介します。
営業ツールとしての信頼感アップ
製造工程や品質管理体制を映像で見せることで、「実際にどのように製品が作られているのか」を直感的に伝えることができ、顧客や取引先に安心感を与えます。
特にBtoBの商材においては、製造元の信頼性が購買判断に大きな影響を与えるため、営業ツールとして活用されるケースが非常に多く見られます。
また、製品導入前に“工場見学”が組み込まれているような取引においても、その前段階の「オンライン工場見学」のような役割として動画が活用されることもあります。商談時に営業担当が動画を提示すれば、説明に説得力を加え、成約につながる後押しとなります。
採用活動での職場環境の可視化
求職者にとって「どんな場所で、どんな人たちと働くのか」は非常に大きな関心ごとです。作業風景や現場スタッフのインタビューなどを映像で伝えることで、入社後のイメージを明確にし、応募者の不安を解消します。
結果として、「安心して応募できる企業」「働きやすそうな職場」といった印象を与えることができ、志望度向上やミスマッチ防止にもつながります。地方メーカーにおいても、動画によって地元の魅力や通勤環境などを伝えることで、採用競争力を高めることが可能です。
Web・展示会・SNSなどでの発信力強化
コーポレートサイトや製品ページに掲載すれば、製品だけでなく“製造の裏側”まで伝えられることで、ユーザーに対する信頼感を高められます。
また、展示会のブースでの放映やSNSでのショート動画展開など、動画を多目的に展開することで、より広い層にリーチしやすくなり、企業としての発信力・可視性の向上にも貢献します。
海外の顧客・パートナーへの説明補助
海外との取引がある場合、言葉や文化の壁を超えて「工場の実態」を伝えるのは容易ではありません。そこで、工場紹介動画が有効なコミュニケーションツールとなります。
ナレーションや字幕を多言語対応にすることで、視覚的な情報とともに伝えたいポイントをしっかり補足でき、グローバルな信頼構築につなげることができます。現地訪問が難しい相手に対しても、信頼性のあるパートナーであることを視覚的に伝える手段として活用できます。
工場紹介動画の基本構成
目的やターゲットに応じて構成は変わりますが、ここでは比較的どの動画にも含まれている内容について紹介します。自社で制作する場合にはどのような内容になるかをイメージしてみてください。
オープニング(会社名・理念・ロゴなど)
冒頭では、会社のロゴや理念、スローガンなどを簡潔に紹介されることが多いです。動画全体のトーンや方向性を印象づけるパートであり、「この動画は何を伝えるものか」を端的に伝える役割を果たします。
また、画としては、ドローンを飛ばして工場全体を俯瞰で撮影したものを見せることが多いです。
製造している製品について
そもそも何を製造している工場なのか?を簡単に説明するパートです。視聴者を想定するとこの部分についてはすでに理解されていることが前提となるため、詳しく説明するというよりはさらっと簡潔な説明になることが多いです。
製造工程の流れ(機械・人の作業)
工場紹介動画の中心となるのがこのパートです。「原料の投入から製品完成」など一連の流れを、機械の稼働や人の手作業を交えて紹介します。スピード感や安全性、整った動線など、製造現場ならではの強みがどこにあるのかを意識することが非常に重要なポイントです。
特長的な技術・品質管理体制の紹介
「この工場ならではのこだわり」や「他社と差別化できるポイント」を伝えるためのパートです。例えば、自社独自の製造技術、高度な品質チェック体制、環境配慮型の生産設備など、無闇にすべてを紹介しようとするのではなく動画の目的や視聴ターゲットを想定した上で視聴者に響く内容を精査し、伝える内容を絞り込むことがポイントです。
働く人のインタビュー
実際に工場で働く社員や技術者の声を届けることで、現場の雰囲気や組織文化がリアルに伝わります。「誰が、どんな想いでモノづくりに取り組んでいるか」を語ってもらうことで、信頼感や親近感を高めることができるため、採用向けの工場紹介動画や、「人手」が重要な製造現場であればぜひ加えたい構成です。
工場紹介動画の事例
動画制作の外注に失敗しないための4つのポイント
動画制作を外注した経験のある人の中には、なんらかの理由で「失敗した」「上手くいかなかった」と感じている方がいます。筆者もお客様からそのような相談を受けたことが何度かあります。
詳細は下記の記事にまとめていますが、ここでは失敗しないために重要な4つのポイントをご紹介します。

適切な制作会社を選ぶ
もちろん発注側としてもそれを強く望んでいると思いますが、
ここで端的にお伝えしたいのは、「信頼できる営業担当者を選ぶ」という視点をもってみることです。
筆者が動画制作に携わり始めた10年ほど前とくらべると動画制作会社は格段に増えました。そしてどの会社も甲乙つけがたいほど豊富な制作実績を持っています。(弊社はまだ会社としての実績は少ないですが…)
その中で何をポイントに選ぶか?の1つのポイントが上記の「信頼できる営業担当者を選ぶ」という視点です。
詳しくは下記の記事にまとめていますが、端的にお伝えすると、

- 優秀な営業担当は、優秀なプロデューサー、優秀なクリエイターをアサインできる
- 優秀な営業担当は、無用なトラブルを避けてくれる
- 優秀な営業担当は、コミュニケーションがスムーズ
という3点です。「絶対この会社がいい!」と思える会社が見つからず悩むことがあればぜひ参考にしてみてください。
そしてもし悩むようであれば、ぜひ筆者にもご相談ください。
スケジュールに余裕を持つ
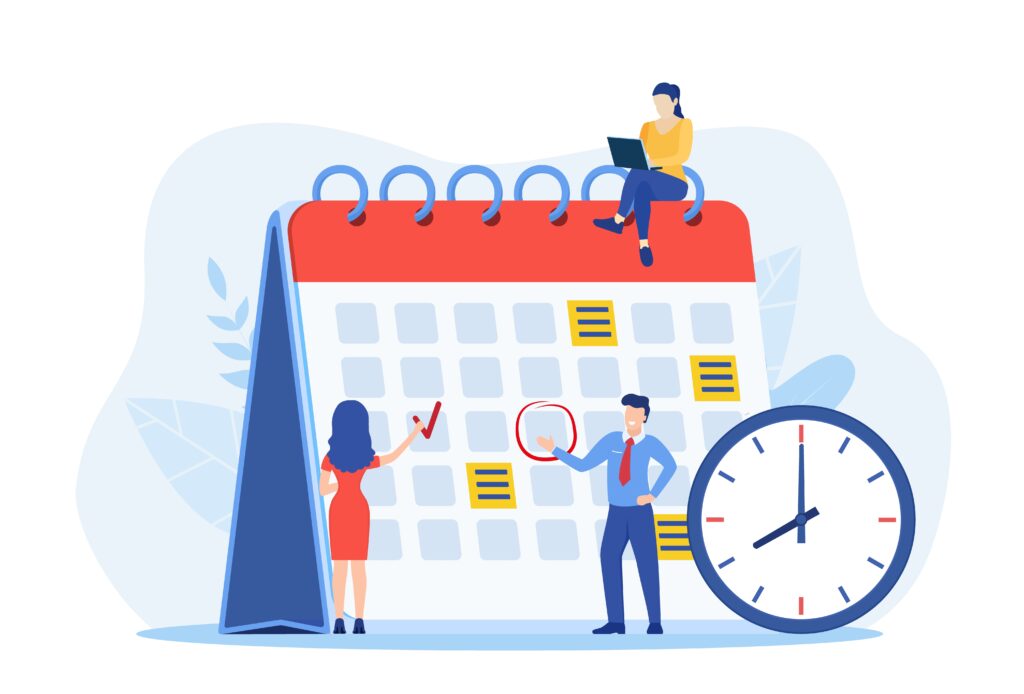
基本的なことではありますが、何らかの理由で急いで制作を進めなければならないケースもあります。そのような場合、
- 人的なリソースを確保するために通常スケジュールでの進行よりもお金がかかる
- 急ぐ分、準備・確認に通常より時間を割くことができず何らかのトラブルが起きる可能性が高くなる
…というリスクがあります。
会社によっては、短納期でも費用を抑えて制作してくれる会社もあるかもしれませんがそれでもスケジュールを短縮するということは、どこかでなにかを犠牲にせざるを得ません。
もちろん、通常スケジュールよりもトラブルが起きる可能性が高まるというだけで、「必ずトラブルになる」「失敗する」わけではありません。制作に慣れているプロが進行する以上、トラブルの種は極力排除し最大限問題なく進行できるよう尽力することは間違いありません。
ただ、それでも想定外のトラブルに見舞われることもあるのが動画をはじめ、クリエイティブ制作の現場です。
だからこそ、できる限りスケジュールには余裕を持つことを強くおすすめします。
制作内容によって変動しますが、工場紹介動画であれば、最低2ヶ月。できれば3ヶ月ほど制作スケジュールが確保できると良いでしょう。
上記はあくまでも「制作期間」なので、制作会社を選んだり正式に発注するまでのリードタイムがどれくらい必要になるかについては、自社の稟議や予算申請のフローについて事前に把握しておく必要があります。
完成イメージをできるだけ具体的にする
いざ、動画制作をスタートする際には制作会社側からどのような動画が完成する予定であるかは絵コンテやシナリオなどの資料を用いて説明があるはずです。
動画制作に慣れていれば、そのような資料で具体的なイメージを持つことができますが、初めての場合にはそれでもイメージが難しいこともあるでしょう。
そのような場合には、遠慮なく制作会社側に質問してイメージの具体化に努めましょう。
制作過程で完成イメージの認識の相違などのズレが生じてしまうと、軌道修正には時間とコストがかかってしまいます。
社内調整を怠らない
発注側の企業の担当者の方の役割の1つが、自社内のステークホルダーとの共通認識の形成です。
- こんな目的でこんな動画を制作します。
- これが完成イメージです。
- いつころ完成予定です。
- このタイミングでシナリオや動画を確認して、いつまでにフィードバックしなければなりません
…などなど、動画制作の背景や前提、クリエイティブイメージ、スケジュールなどについて関係者としっかりと「握る」ことができていないと、後になって「どんでん返し」が起きることは珍しいことではありません。
特に、動画制作について最終的なOKを出せる決裁権者とのすり合わせは重要です。
最後に
工場紹介動画は、企業の信頼性を高め、営業・マーケティングにおいて強力なツールとなります。しかし、制作のプロセスを誤ると、効果が半減してしまう可能性があります。
本記事で紹介した「失敗しないためのポイント」を押さえ、効果的な工場紹介動画を制作しましょう。
情報整理や予算の検討などの事前準備がご不安な方は筆者がお手伝いいたします。
是非、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。