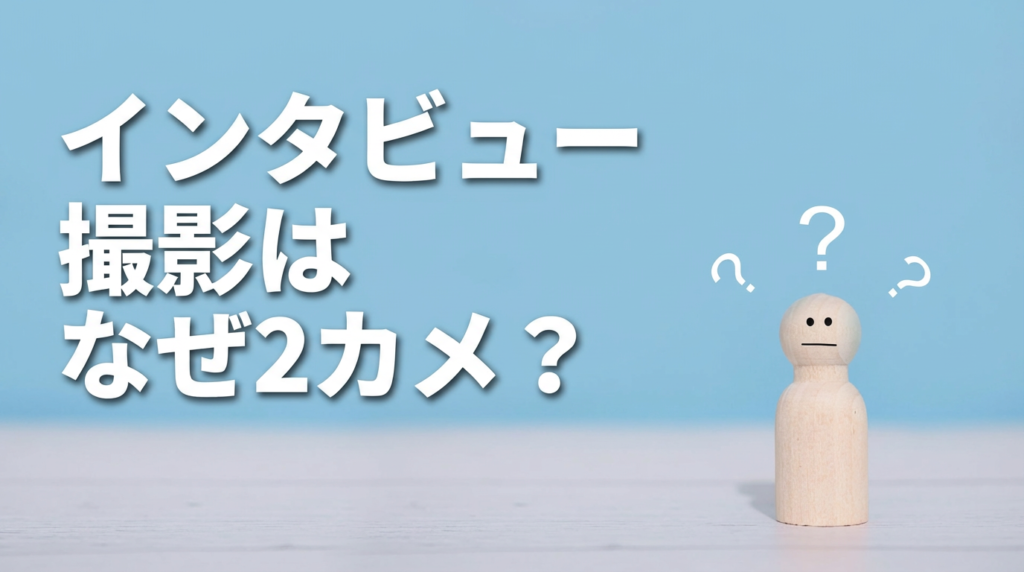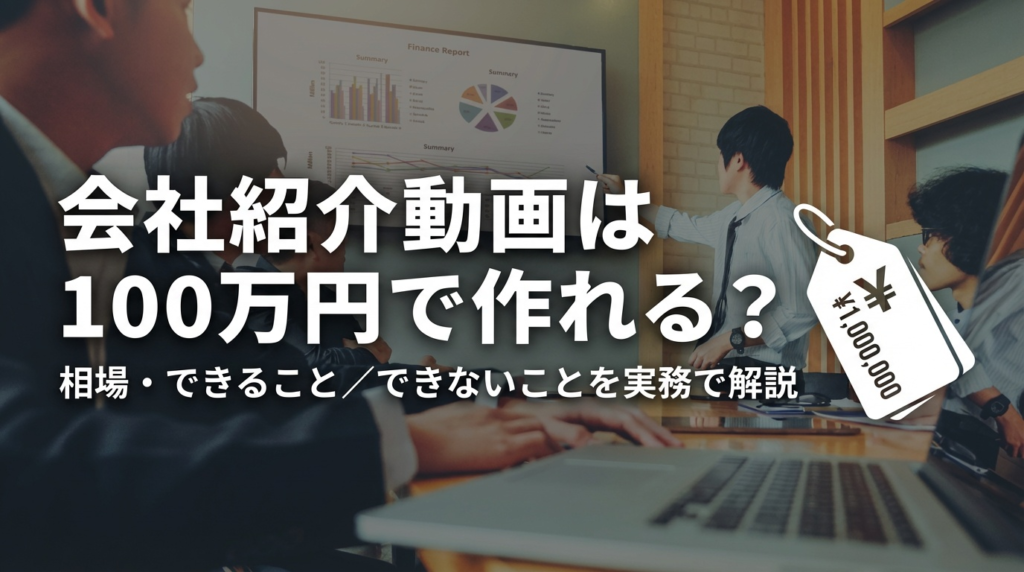期末が目前に迫り、「余っているわけではないけれど、使える予算がある…」という状況に心当たりはありませんか?
私たちはこれまで多くの動画制作をご依頼いただく中で、毎年必ず、期末の残予算をきっかけにご相談くださる法人担当者の方々と向き合ってきました。
その経験から、動画制作は“予算消化の手段”として非常に有効な選択肢であると自信を持って言えます。
ただし、残予算だからといって目的や活用方針が曖昧なまま進めてしまうと、せっかく制作した動画が“使われない資産”になってしまうリスクも。
本記事では、動画制作を「単なる消化施策」に終わらせず、中長期で価値を生む“投資”へと昇華させるための考え方と実践アイデアを、事例も交えて解説します。
筆者のプロフィール
動画制作会社(予算数十万円〜数百万円)での営業兼プロデューサーとしての役割を中心に、広告代理店(予算数百万円〜数千万円)でのアカウント(クライアントと社内クリエイティブチームの窓口、PM業務を担当する役割
なども経験しているため、比較的高い説得力で本記事をお届けできるのではないかと考えています。
1. 法人の残予算の使い道として、動画制作がおすすめである理由
それはずばり、「汎用性の高さ」です。
動画コンテンツは、一度制作すれば終わりではなく、さまざまな場面で繰り返し活用できるという特徴があります。
たとえば、営業ツールとして活用する、採用ページに掲載する、展示会で流す、SNSで広告配信する——こうした用途を“1本の動画”でカバーできる可能性があります。
これは、紙のパンフレットやノベルティなど、一度使ったら終わりの施策とは大きく異なる点です。
また、社外向けだけでなく、社内マニュアル・社員教育・インナーブランディングなど、社内施策として活用するケースも増えています。実際、年度末の予算で制作した社内向け動画が、翌年度以降も継続して活用されているという事例は少なくありません。
このように動画は「今使う」だけでなく、“来年度以降も役立つ資産”として残せるのです。
さらに、動画の中身を再編集して、用途別に展開することも可能です。たとえばサービス紹介動画をベースに、広告用の短尺版、採用サイト向けの抜粋版などを制作することで、1つの制作物が複数の成果を生む構成にもなり得ます。
こうした柔軟な展開を前提に「どうすれば無駄なく使い倒せるか?」までを見据えて設計することが、予算消化での動画制作を“投資”に変える鍵であり、動画が残予算の使い道としておすすめできる理由です。
2.動画を有益な資産にするためのポイント

動画を中長期で活用できる有益な資産とするために欠かせないのが、「情報整理・情報設計」です。
残予算を執行する際には、どうしても制作期間が短いケースが多くなりますが、それでもできる限り丁寧に情報整理・設計ができるか否かで制作した動画の寿命が決まると言っても過言ではありません。
では、具体的にはどのように行うとよいのでしょうか。
これは特別なことをする必要はなく、いわゆる5W1Hで考えればOKです。ただし、できるだけ丁寧に・深く考えることがポイントです。
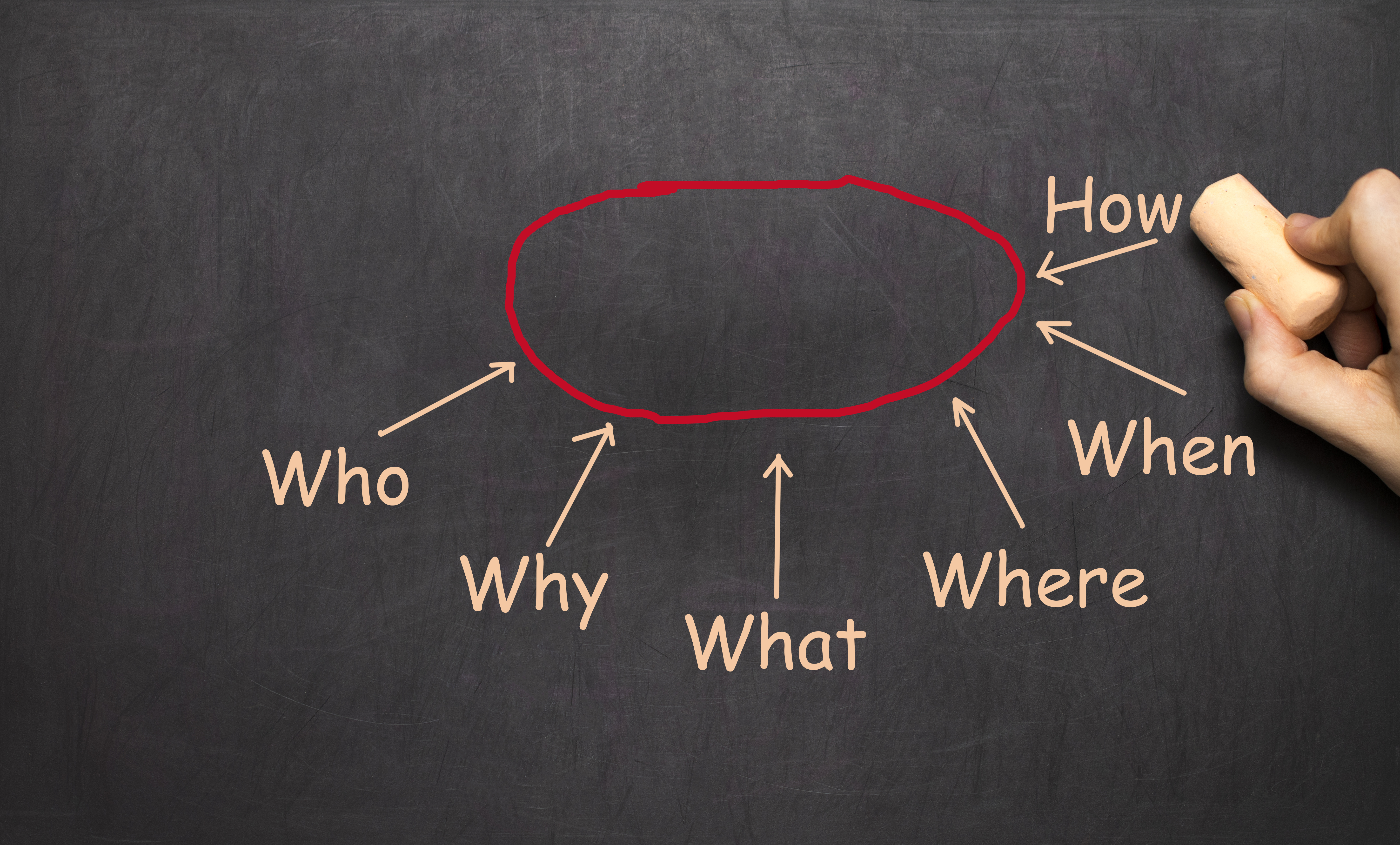
丁寧に・深く。とは?
丁寧に・深くというのは、例えば動画のターゲットに当たる「Who」について。
視聴ターゲットが企業の採用担当者だとすると、
・その企業の規模や、採用人数はどれくらいか?
・その企業の採用ターゲットはどんな人か?
・その採用担当者はどんなことに困っているのか?
・動画で訴求する内容は、ターゲットの何を解決できるのか?
・動画を視聴したあとに、ターゲットはどんな心情を抱くのか?
…などなど、単に「ターゲット」を設定するだけではなく、そのターゲットの状況や抱えている課題、心情などをできる限り明確にする必要があります。
※ここではWhoを例に挙げましたが、When(視聴タイミング)やWhat(伝えたいこと)なども同様に掘り下げておくことで、訴求力のある動画が設計しやすくなります。
情報整理が比較的ラクなパターン
一方で、期末のタイミングで丁寧に情報を整理し、社内で共通認識を形成する時間がない…という場合には「会社紹介」や「顧客インタビュー」など、
・広くあまねく情報を届けるための動画
・情報整理を行うまでもなく、訴求したい内容が明確である動画
のいずれかを検討すると良いでしょう。
広くあまねく情報を届けるための動画
例えば、いわゆる「会社紹介動画」などが該当します。会社について紹介する動画であるため、細かくターゲットを分析して訴求ポイントを検討するというよりは、色んな人が視聴するので、誰が観てもある程度理解してもらえるもののほうが好ましいため、情報整理に時間をかける必要はありません。
訴求したい内容が明確である動画
例えば、顧客インタビューの動画などが該当します。特定の製品やサービスを利用してくれている顧客へのインタビュー動画の場合、それを制作すると決めた時点で、前述した「Who」についての情報はほぼ自動的に決まってしまうと言えます。
そのため、撮影に協力してくれる顧客さえ見つけることができれば、情報整理に時間をかけることなくスムーズに制作をスタートすることが可能です。
3.短納期で動画を制作するためのポイント
期末などのタイミングで残予算を活用する場合、必然的に制作期間が短くなります。
通常よりもタイトなスケジュールになることで、コストやクオリティ面でのトレードオフが発生しやすくなりますが、それらを最小限に抑えるための工夫は可能です。
特に効果的なのは、以下の3点です。
- 制作会社をあらかじめ1社に絞って相談する
- 発注前に社内で情報を整理・共有しておく
- 制作物の確認フローを明確にしておく
すべてを実行できれば理想的ですが、いずれか1つでも実行できれば、スケジュール上のリスクは大きく軽減されます。
1.制作会社をあらかじめ1社に絞って相談する
通常は、複数の制作会社に声をかけて商談を行い、提案と見積書を比較検討するのが一般的です。
しかしこのプロセスには、最短でも2週間程度を要することが多く、短納期の案件では大きなネックとなります。
そのため、あらかじめ信頼できる1社に絞って相談を進めることで、この選定プロセスにかかる時間をまるごと削減できます。
もちろん、1社に決め打ちで発注することに不安を感じる場合もあるでしょう。
その場合は、下記のようなステップもおすすめです。
- 複数社と一度面談を実施する
- 実績や担当者の対応を比較した上で、もっとも信頼できる1社に絞り込む
事前にWebサイトやポートフォリオを確認しておけば、各社のクオリティ水準や得意領域はある程度把握できます。加えて、実際に窓口となる担当者との対話から、柔軟性・提案力・対応スピードなどを確認しておけば、発注リスクは大幅に低減できます。

2.発注前に情報を整理・共有しておく
動画制作の準備段階において、もっとも重要なのが「情報整理」と「共通認識の形成」です。
この情報整理が発注前に完了しているか否かで、制作のスムーズさは大きく変わります。
特に意識したいのは、以下の2点です。
- 訴求したい内容・ターゲット・目的を明確にすること
- 社内関係者(上司や他部署)とのすり合わせを済ませておくこと
情報整理のフォーマットはExcelやWordなど、形式にこだわる必要はありません。
ポイントは、制作会社に渡した際に「すぐに概要が理解できる状態」になっていることです。
内容が整理された資料さえあれば、ヒアリングの時間を大幅に短縮でき、即見積もり対応が可能になります。
3.制作物の確認フローを明確にしておく。
動画制作の工程では、以下のように複数のアウトプットが段階的に発生します。
- シナリオ
- 絵コンテ
- BGM・ナレーション案
- 完成動画
この各段階において、「誰がどの段階で最終判断を下すのか」という確認フローが不明瞭だと、手戻りの原因になります。
特に注意したいのは、担当者レベルではOKを出していたにも関わらず、最終段階で責任者の意見によって修正が発生するケースです。
このようなケースでは、場合によってはシナリオ段階にまで戻ることになり、納期やコストに大きく影響を及ぼします。
そのため、制作開始前に以下を整理しておくことをおすすめします。
- どの段階で誰が確認・判断するか
- どの工程が「担当者判断で完結できるか」
- どの工程が「責任者への確認が必須か」
この点を明確にしておくことで、社内調整のスピードが上がり、制作会社側の作業もスムーズに進行します。
4.短納期で制作可能な動画のポイントと事例

短納期で制作しやすい動画の特徴
アニメーション・モーショングラフィックス動画
- 短い尺
- カット数/シーン数が少ない
- 動き(アニメーション)が比較的シンプル
実写
- 撮影場所・日数が少ない
- 撮影場所が自社(発注側企業)オフィスなど、許可取りや手配が容易
- 撮影する人数、スタッフの数が少ない
- キャスティング(プロの役者やモデル、エキストラなど)が不要
共通するのは「工数が少ない」ということなので、上記の様な条件を満たすものは短納期でも制作しやすいと同時に、比較的費用も抑えやすいと言うこともできます。
短納期でも制作可能な動画事例
短納期でも比較的制作しやすい事例をアニメーション・実写それぞれで紹介します。必ずしも前述の条件を満たすものではありませんが、ご参考ください。
アニメーション・モーショングラフィックス
実写
動画制作はcaseへご相談ください。
とても長くなりましたが、ここまでお読み頂きありがとうございます。
もし、この記事を読んで「いいな」と思えたらぜひ弊社caseへ動画制作についてご相談ください。
情報整理や予算の検討などの事前準備がご不安な方は筆者がお手伝いいたします。
是非、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。