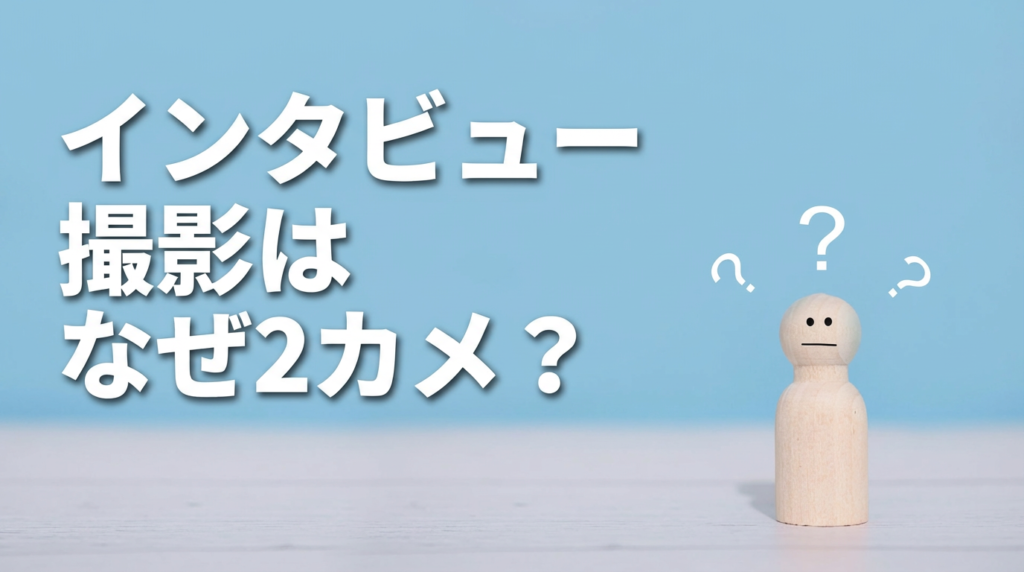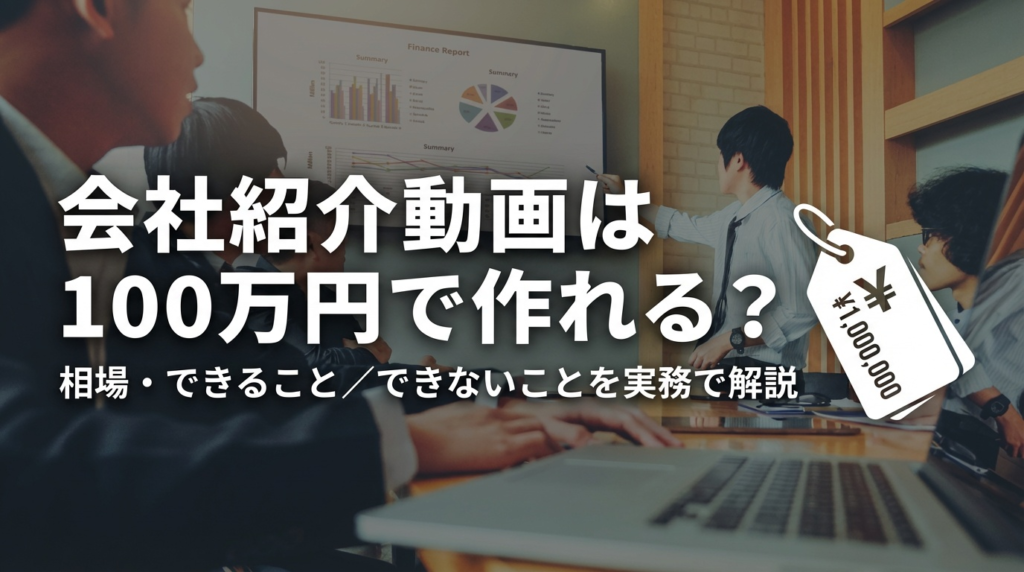はじめに|動画制作は、発注前から始まっている
動画を活用したマーケティングや営業支援が一般化する中、「とりあえず動画を作ろう」と検討を始める企業も増えてきました。
しかし、実際にご相談をいただくなかで感じるのは、「動画制作は、発注した瞬間に始まるわけではない」ということです。
制作をスムーズに進め、成果につながる動画をつくるためには、実は“発注前”の段階が非常に重要です。
このタイミングでのちょっとした見落としが、あとから“ズレ”となって表面化し、手戻りや失敗につながることも少なくありません。
たとえば──
- 動画を使って何を達成したいのかが曖昧なままスタートしてしまう
- 完成イメージが社内で共有できておらず、途中で「やっぱり違う」と言われてしまう
- 見積もりの金額だけで会社を選んだ結果、納品されたものが使いづらい
- 制作会社の実績を見て安心していたら、実際の担当者との意思疎通が難しかった
こうした“あるある”は、決して発注側の落ち度ではありません。
むしろ、初めて発注する立場だからこそ起きやすい落とし穴と言えます。
本記事では、そんな発注時によくある6つの落とし穴を整理し、それぞれにどう向き合えばよいか、実務に即した形でご紹介していきます。
「はじめて動画を発注するが、何をどう準備すればいいかわからない」
「過去に発注したときにうまくいかなかった理由を明確にしたい」
そんな方にとって、納得感のある制作につなげるヒントとなれば幸いです。
筆者のプロフィール
まず、この記事を読んでいただくにあたって「誰が何を書いているのか?」も非常に重要な要素になると思いますので、簡単に私のプロフィールをまとめています。

【株式会社case 代表取締役/動画制作プロデューサー:加藤智史】
新卒で入社した動画制作会社で広告・マーケティング・採用・人材研修など約400本の動画制作に携わる。その後、TVCMなどの制作を行う、大手制作会社にアカウントエグゼクティブとしてジョイン。数千万円規模のプロモーション案件に携わり、動画にとどまらないクリエイティブ制作やプロジェクトマネジメントを経験。現在は本メディアの運営を通じた企業動画の受託制作や、動画制作会社の営業支援などを行う。
動画制作会社(予算数十万円〜数百万円)での営業兼プロデューサーとしての役割を中心に、広告代理店(予算数百万円〜数千万円)でのアカウント(クライアントと社内クリエイティブチームの窓口、PM業務を担当する役割)なども経験しているため、比較的高い説得力で本記事をお届けできるのではないかと考えています。
落とし穴①:目的がふわっとしている
「まずは動画をつくってみよう」「とりあえずLPに載せたい」。
動画制作のご相談で、最初に出てくる言葉としてよくあるものです。
もちろんその気持ちは自然なもので、動画活用を推進する一歩として歓迎すべき姿勢です。
ですが、この“目的がふわっとした状態”のまま進行してしまうと、制作中に迷走しやすくなります。
たとえば──
- シナリオが定まらず、打ち合わせを重ねても方向性が固まらない
- メッセージがぼやけて、誰にとっても“なんとなく良い”だけの動画になる
- 関係者によって言っていることがバラバラになり、合意形成が難しくなる
このような状況に陥ると、修正のやり直しが多くなり、結果として納期もコストも膨らむリスクがあります。
▶ 回避法:目的+動画の「役割」をセットで考える
動画を制作する前に、「なぜ今、この動画が必要なのか?」を一度立ち止まって整理してみましょう。
以下のように、「動画の目的」と、それに対して「動画が担うべき役割」をセットで考えるのがポイントです:
- 目的:LPのコンバージョンを上げたい → 役割:冒頭でサービスの価値を直感的に伝え、離脱を防ぐフックになる
- 目的:営業現場での説明を省力化したい → 役割:概要やユースケースを短時間で伝え、商談の質を上げる補助ツール
- 目的:展示会でのブース訴求を強化したい → 役割:短時間で注目を集める演出+雰囲気重視のブランディング要素
このように、「目的→役割」の因果関係を明確にすると、構成・尺・演出・表現トーンすべての判断軸がぶれません。
また、動画だけですべてを語ろうとせず、「この動画は何の補完をすべきか?」という視点も非常に大切です。
“主役”として機能するのか、“補助”として機能するのかで、構成もまったく変わってきます。
落とし穴②:ターゲットや訴求が曖昧
動画の目的が定まったとしても、「誰に向けて何を伝えるか」がぼんやりしていると、訴求力の弱い動画になってしまいます。
実際に多くの現場で起こりがちなのが、「ターゲット」が明確に定まっておらず、制作側も関係者も何となく進めてしまうパターンです。
その結果──
- 想定していた視聴者と動画のトーンが合わず、ピンとこない仕上がりになる
- 複数のメッセージが詰め込まれて、何が主役か分からない構成になる
- 視聴後に「で、結局どうすればいいの?」と行動につながらない
という状態になってしまいかねません。
▶ 回避法①:「誰に向けているか?」を、行動と感情で整理する
ターゲットの設定は、「属性」だけでなく「状態」を意識することが重要です。
例:
- 新しいSaaSのサービス紹介動画 → 対象:中小企業の情報システム担当者(属性) → 状態:まだサービスカテゴリを知らない/導入検討のきっかけを探している(心理)
この場合、訴求すべきは「機能の優位性」よりも、「なぜこのサービスカテゴリが今必要か」といった“気づき”の提供です。
▶ 回避法②:「何を伝えるか?」ではなく「どう感じてほしいか?」から逆算する
「この動画を見た視聴者に、どう思ってほしいか」「どんな印象を残したいか」を先に考えると、訴求の軸がぶれにくくなります。
例:
- “分かりやすい”と感じてほしい
- “信頼できそう”と思ってほしい
- “おもしろい/センスがある”と思ってほしい
- “自分にも関係ありそう”と感じてほしい
こうした感情の設計ができていると、演出トーンやコピーの表現、ナレーションの語り口など細部にも一貫性が生まれます。
落とし穴③:完成イメージが言語化できていない

動画制作において「なんとなくこういうのがいい」という感覚は、誰しも持っています。
しかしこの“なんとなく”のまま進めてしまうと、制作サイドとの認識のズレが発生しやすく、後半で大きな修正が必要になるケースもあります。
よくある表現として、
- 「他社と違う感じにしたい」
- 「オシャレで、信頼感もある感じ」
- 「スタートアップらしさを出したい」
などがありますが、これだけでは制作側が具体的なアウトプットに落とし込むことができません。
▶ 回避法①:参考動画を複数集めて「言語化の軸」をつくる
最も有効なのは、イメージに近い動画を複数ピックアップして共有することです。
ただし、単にURLを共有するだけでは不十分で、
- どこが好きか(演出?色味?ナレーション?構成?)
- なぜ参考になるのか(ターゲットが近い?演出のテンポ感?)
- 自社に合っている/合っていない部分はどこか
といったコメントを添えておくことで、制作側の理解度は格段に高まります。
▶ 回避法②:「完成イメージは曖昧でOK」と割り切って、任せるという選択肢も
逆に、「どんな動画が自社にフィットするのか、まだよくわからない…」という場合もあります。
そのときは、無理に完成イメージを決めようとせず、動画の目的・役割・ターゲット像だけを明確にし、それをもとに構成案や絵コンテを提案してもらうという進め方も有効です。
経験豊富な制作会社であれば、「目的 × ターゲット × 活用シーン」から、イメージに合う構成・演出を逆算してくれます。
落とし穴④:社内確認のフローが整理されていない
動画制作がスムーズに進まない理由のひとつに、「社内調整の遅れ」があります。
構成案や絵コンテ、ナレーション原稿、仮編集データ──
各フェーズで制作会社から「ご確認をお願いします」と連絡が来るたびに、社内ですぐに判断ができず、確認が後ろ倒しになってしまう。これは非常によくあるパターンです。
さらに厄介なのは、一度合意した内容に対して、後から“上からのひと言”が入り、方針が変わってしまうこと。
この“どんでん返し”が起きると、制作全体に大きな遅延ややり直しが発生し、追加費用がかかるケースも出てきます。
▶ 回避法①:決裁者と関係者を事前に整理しておく
動画制作を発注する前に、以下のような社内の体制を明確にしておくことをおすすめします。
- 誰が最終的なOKを出すのか?(決裁者)
- 誰がどのタイミングでレビューするのか?(関係者)
- どのレベルまで確認が必要か?(内容/トンマナ/構成のみ等)
これを把握しておくことで、「この段階で決裁者に確認をとる必要がある」という判断がしやすくなり、無駄な手戻りを防ぐことができます。
▶ 回避法②:確認スケジュールを制作会社と共有しておく
制作側も、社内調整が必要なのは理解しています。
だからこそ、「この日までに確認がほしい」というスケジュールの握りを、制作スタート時に行っておくとお互い安心です。
たとえば:
- 構成案提出 → 3営業日以内にフィードバック
- 仮編集チェック → 5営業日以内に修正点をまとめる
- 最終納品前 → 上長含めた最終確認を設定しておく
こうした“確認の設計”も進行管理の一部と考えると、発注側としてもプロジェクトマネジメントの質がぐっと上がります。
落とし穴⑤:見積もりの“安さ”だけで制作会社を選ぶ

複数社に相見積もりを取ったとき、「一番安い会社に頼めばコスパがいいだろう」と考えるのは、ある意味当然の流れです。
しかし、動画制作の見積りは、想定されている条件によって大きく変動するということは、経験者ほどよく知っています。
実際に以下のようなトラブルが起きることも少なくありません。
- 価格は安かったが、構成の提案や演出面での相談にはあまり乗ってもらえなかった
- 修正回数に制限があり、社内調整と合わずに想定外の追加費用が発生した
- 納品物はきれいだが、“誰に何を伝えたいか”の意図が反映されていない
- 担当者と意思疎通がうまくできず、対応に不安が残った
いずれも、当初の「安いから」という判断だけで制作会社を選んだ結果として起きがちなことです。
▶ 回避法①:「見積もりの背景」を理解する
見積書には、金額以上に「何にどれだけ手間と時間をかけるか」という制作会社の方針が反映されています。
たとえば:
- 企画・構成の提案まで含まれているのか
- 修正回数や対応範囲に制限があるのか
- ディレクターやプロデューサーはどこまで伴走してくれるのか
- 編集だけでなく、目的整理や活用方法の相談も可能か
こうした点を確認し、「安い理由」と「高い理由」が納得できるかどうかを判断軸にしましょう。
▶ 回避法②:「成果を出すために必要な支援」を基準に選ぶ
予算はもちろん重要ですが、「そもそもこの動画で何を達成したいのか?」という目的に照らして考えると、
価格の安さよりも「伴走してくれるかどうか」の方が結果的に重要であるケースは多いです。
最初の数万円を削っても、修正のやり直しや社内の不信感が増せば、見えないコストが膨らむことにもなりかねません。
落とし穴⑥:制作会社の“実績”だけで判断してしまう
動画制作会社を選ぶとき、「有名企業の実績があるから安心」「制作実績の数が多いから信頼できる」といった理由で発注先を決めるケースは少なくありません。
たしかに、豊富な実績は一つの判断材料になりますし、安心感を与えてくれる要素でもあります。
ただし、「誰がその実績を担当したのか」までは、実績ページからは見えてこないというのが注意すべきポイントです。
▶ 実績よりも大事なのは「誰が担当するのか」
動画制作は、多くの場合プロジェクトごとに担当者が異なります。
つまり、同じ会社であっても、提案の深さ・進行管理の丁寧さ・構成の精度は担当者次第ということです。
特に重要なのが「営業(プロデューサー)」の力量です。
- ヒアリング力があるか
- 要望を噛み砕いて整理し、動画に落とし込む力があるか
- 社内調整や目的整理まで、伴走してくれるか
- トラブルや変更時に冷静かつ柔軟に対応できるか
これらの要素は、実績一覧には現れませんが、実際の進行においては決定的な差を生みます。
▶ 回避法:実績だけでなく「担当者との対話」で判断する
制作会社を選ぶ際には、見積もりだけでなく「初回打ち合わせ」や「問い合わせ時の対応」も含めて、“人”を見て判断することをおすすめします。
- こちらの課題に対して、質問を掘り下げてくれるか?
- 表面的な提案ではなく、構成や目的設計に踏み込んでくれるか?
- 懸念点や課題を先回りして整理してくれるか?
こうした姿勢が見えるかどうかが、実績よりも確かな判断材料になるはずです。
caseでは、営業担当がそのまま制作のプロデューサーとして案件を伴走しています。
だからこそ、受注前から「どうすれば伝わる動画になるか?」を一緒に考え、構成設計から納品まで責任を持って進行できます。
まとめ|発注前の準備が動画の成否を決める
動画制作は「発注してからがスタート」ではなく、発注する前の準備こそが、成功の8割を決めるプロセスです。
今回ご紹介したように、よくある“落とし穴”はどれも、決して特別なケースではありません。むしろ、誰にでも起こりうるごく自然なつまずきです。
- 目的があいまいなまま進めてしまう
- 視聴者や訴求内容が整理されていない
- 完成イメージを共有できないまま制作が始まる
- 社内調整が想定外の手戻りを引き起こす
- 安さや実績だけでパートナーを選んでしまう
これらを回避するために必要なのは、「すべてを完璧に準備すること」ではありません。
“どこまでを自分たちで考えておき、どこからをプロに任せるか”を見極めることです。
▶ caseでは、発注前からご相談いただけます
「まだ発注が確定しているわけではないけど…」
「社内で企画を通す前に、プロの意見を聞いておきたい」
「動画をつくるべきかどうか、まず判断したい」
そういった段階からでも、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
私たちは「動画をつくること」ではなく、「動画を活かすこと」をゴールにしているからこそ、企画・構成の整理や社内調整の進め方も含めてサポートできます。
動画制作のスタートラインは、“問い合わせフォームの送信”ではなく、最初の一歩を踏み出すその瞬間からです。
迷った時は、ぜひ早めにご相談ください。早い段階からの伴走が、動画の価値を最大化する近道です。