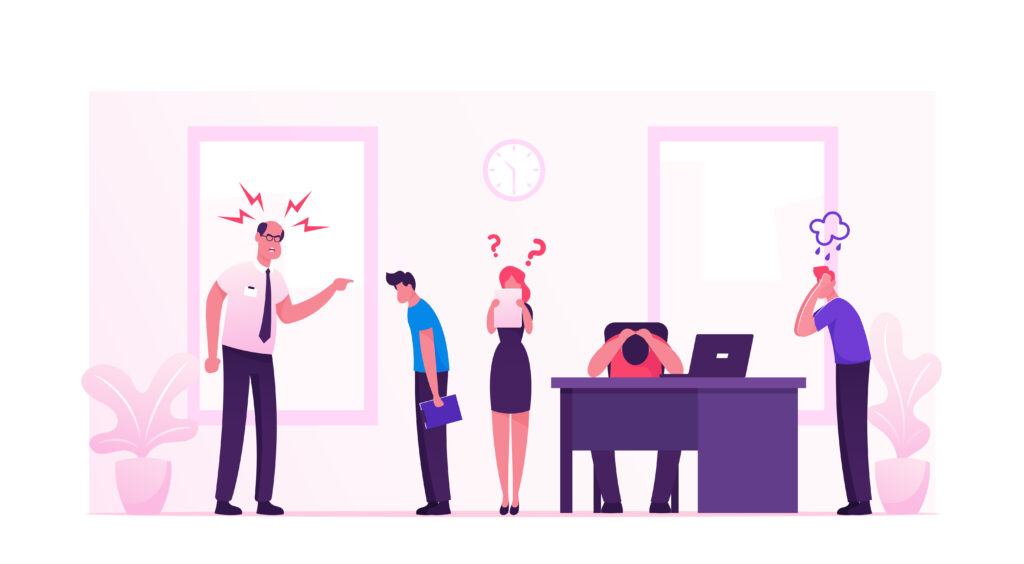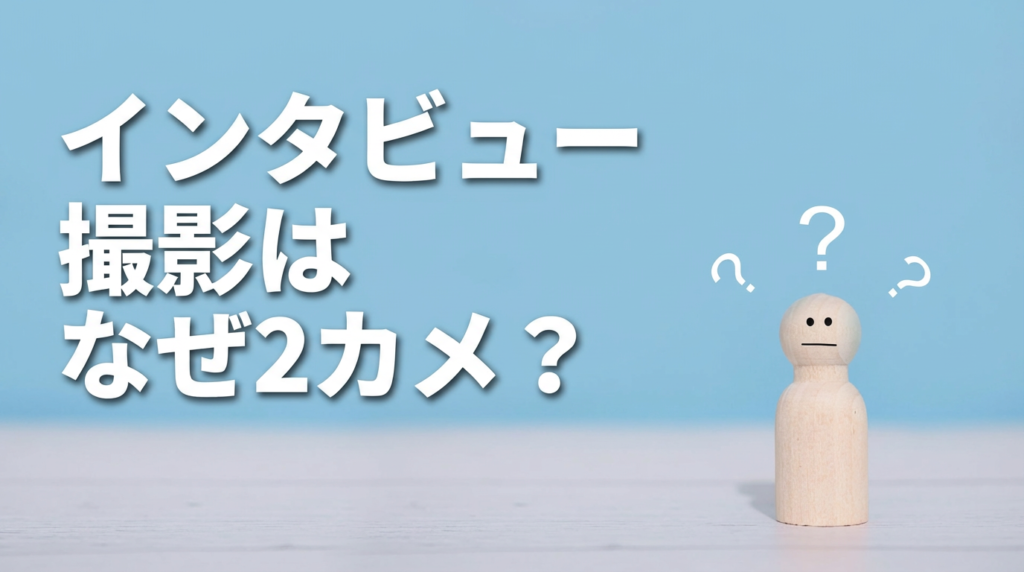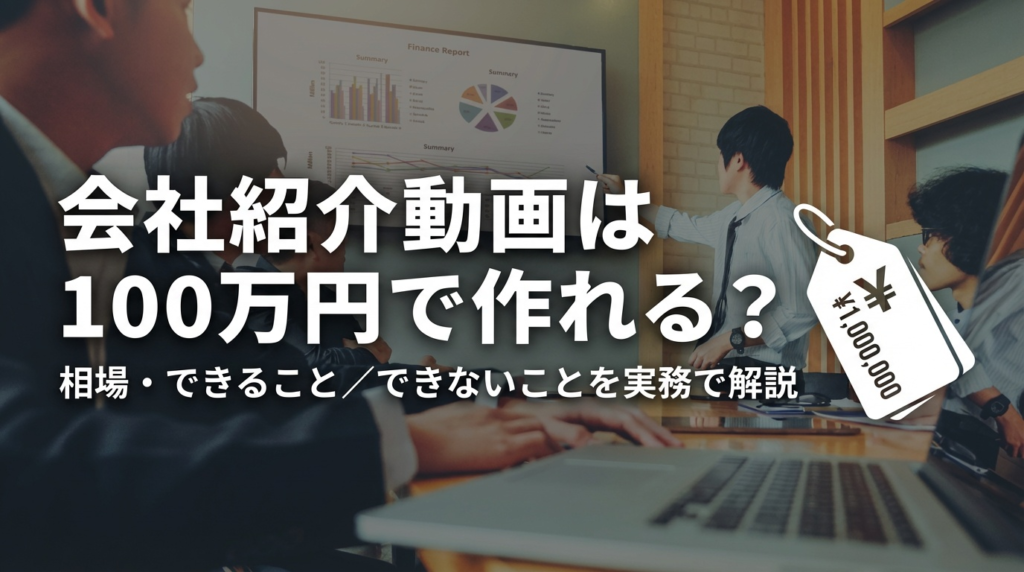サービス紹介動画は、SaaSやITサービスなど無形商材を扱う企業にとって、わかりやすさや信頼感を高める有効なツールです。ただし、「とりあえず動画を作ってみよう」と勢いで進めてしまうと、完成したものが思ったほど使えなかったり、伝えたいことがぼやけてしまったりするケースも少なくありません。
特に、初めて動画を発注する場合には「何をどこまで準備すればよいのか」が見えづらく、構成や制作プロセスの中で方向性のズレが生まれてしまうことがあります。結果として、やり直しが発生したり、時間とコストが無駄になってしまったりすることにもつながりかねません。
だからこそ重要なのが、事前に決めるべきこと・考えておくべきことを、整理して共通認識を形成することです。
本記事では、サービス紹介動画を失敗なく制作するために、発注前の段階で整理しておきたい3つの視点を解説します。これから動画制作を検討されている方にとって、スムーズな進行と納得感ある仕上がりを実現するためのヒントになれば幸いです。
筆者のプロフィール
まず、この記事を読んでいただくにあたって「誰が何を書いているのか?」も非常に重要な要素になると思いますので、簡単に私のプロフィールをまとめています。

【株式会社case 代表取締役/動画制作プロデューサー:加藤智史】
新卒で入社した動画制作会社で広告・マーケティング・採用・人材研修など約400本の動画制作に携わる。その後、TVCMなどの制作を行う、大手制作会社にアカウントエグゼクティブとしてジョイン。数千万円規模のプロモーション案件に携わり、動画にとどまらないクリエイティブ制作やプロジェクトマネジメントを経験。現在は本メディアの運営を通じた企業動画の受託制作や、動画制作会社の営業支援などを行う。
動画制作会社(予算数十万円〜数百万円)での営業兼プロデューサーとしての役割を中心に、広告代理店(予算数百万円〜数千万円)でのアカウント(クライアントと社内クリエイティブチームの窓口、PM業務を担当する役割)なども経験しているため、比較的高い説得力で本記事をお届けできるのではないかと考えています。
よくあるQ&A
- サービス紹介動画の制作費はどれくらい必要?
-
制作体制や内容によって大きく変動しますが、50万円〜200万円程度で制作されることが多いです。
- サービス紹介動画の製作期間はどれくらい?
-
約1.5-2ヶ月ほどを想定しておくと、無理のないスケジュールだと言えます。
視点①|「この動画は何のためにつくるのか?」目的の明確化
動画制作で最初に考えるべきことは、「この動画をつくる目的は何か?」という点です。
サービス紹介動画とひとことで言っても、その用途はさまざま。たとえば以下のように、目的によって構成や訴求内容は大きく変わってきます。
- LPに掲載して問い合わせ数を増やしたい
- 展示会やセミナーでサービスの全体像を短時間で伝えたい
- 営業担当が提案時に使えるツールがほしい
- サービスの世界観やブランドイメージを明確に伝えたい
- SNSや動画広告での認知獲得につなげたい
この「目的」が曖昧なまま制作をスタートしてしまうと、構成やトンマナの判断がブレたり、関係者の意見が分かれて方向性が定まらなかったりすることが多くあります。
結果として、「完成したけれど、何に使うべきかがはっきりしない」「見た目は綺麗だけれど、社内ではあまり活用されていない」といった状況になってしまうことも。
そして、この目的だけではなく、目的を達成するために動画が担う役割も設定するのが重要なポイントです。
例えば、LPにただ動画を掲載しても問い合わせ数を増やすことは難しいです。
- そもそも、現状のLPからの問い合わせはもっと増やせるポテンシャルがあるのか?
- ポテンシャルを活かしきれてない要因、問い合わせが増えない要因はどこにあるのか?
- その要因はどうすれば解消できるのか?
…などを考えたうえで、動画の役割を設定することが重要です。
具体的には、
- 動画を見ることで、サービスの概要を理解してもらい、LPの情報をキャッチアップしてもらうためのフックにする
- 動画を見ることで、得られるベネフィットを理解してもらい、LPの情報をキャッチアップしてもらうためのフックにする
- 動画を見ることで、サービスの世界観を理解してもらい、共感してもらう
…などです。
動画ですべての情報を伝えて、ユーザーの意思決定を促すことはできません。
そもそもの課題を整理した上で、動画でアプローチするべきポイントを定め、それを役割として設定することが重要です。
視点②|「誰に何を伝えたいのか?」ターゲットと訴求ポイントの整理
ターゲットを整理する
動画を通じて伝えたいことを明確にするためには、「誰に向けて発信するのか?」という視点が欠かせません。
同じサービスを紹介する動画であっても、視聴者が誰かによって、適切な言葉選びや構成は大きく変わってきます。
たとえば、以下のように視聴者によってアプローチは異なります。
- 潜在顧客に向けてなら…「何のサービスなのか」「どんなメリットがあるのか」を端的に
- 既存ユーザーに向けてなら…新機能や活用例など、具体的なユースケースを重視
- 社内関係者や経営層に向けてなら…導入の意義や投資対効果、他社導入実績などを重視
- パートナー企業に向けてなら…協業メリットや展望など、信頼構築を意識した構成に
また、ターゲットは必ずしもその製品やサービスを「買って欲しい人」とは限りません。
その製品やサービスが、新規性の高いものであれば、いわゆる「アーリーアダプター」なのか、「レイトマジョリティ」なのか。
製品やサービスのターゲットの中でも更に絞り込まれるケースもあります。
この点については、前述の「動画の役割」とも深くリンクする部分です。
訴求ポイントを整理する
ターゲットが明確になったら、次に重要なのが「何を伝えるか=訴求ポイント」の整理です。
ここでありがちなのが、伝えたいことをすべて盛り込みたくなってしまうこと。
サービスの機能、実績、想い、競合優位性…すべて大事に見えますが、**動画は「限られた尺で伝えるメディア」**であることを忘れてはいけません。
動画はあくまで「きっかけ」をつくるツールです。
その後の資料ダウンロードや問い合わせ、商談など、次のアクションにつなげるために“何を一番伝えるべきか”を決めることが重要です。
訴求ポイントの考え方(例)
- サービスのメリットやベネフィットを最優先で伝えるべきか?
- 他社との違い(競合優位性)を強調すべきか?
- 導入のしやすさ・費用対効果を打ち出すべきか?
- 共感や信頼感を生む世界観・ブランドメッセージを届けるべきか?
訴求ポイントの優先順位を間違えると、“伝わるけど響かない動画”になってしまうことも。
「この視聴者にとって、今知ってほしいことは何か?」という視点で整理することが大切です。
どうしても絞り切れない場合は…
「どれも大事で絞れない」という場合は、動画の活用シーンごとに複数パターンを作ることも検討しましょう。
たとえば:
- LP用に1分の導入動画
- 営業ツール用に2分の機能紹介
- 展示会用に目を引くビジュアル中心の動画 …など
1本で“全部”をカバーしようとせず、動画の役割と使い方に合わせて訴求内容を整理するのが、結果的に効果的な使い方につながります。
このように「ターゲット」と「訴求ポイント」を整理しておくことで、動画制作の方向性がブレにくくなり、社内外での合意形成もしやすくなります。
視点③|どこまで準備できるか?予算とスケジュールの見極め
サービス紹介動画の制作は、「どれくらいの予算をかけられるか」「どのくらいの期間で完成させたいか」によって、できることや提案の幅が大きく変わってきます。
この2つの条件を事前にある程度整理しておくことで、制作会社からの提案も具体的になり、スムーズに進行できる可能性が高まります。
予算によって変わること
サービス紹介動画は、モーショングラフィックスやアニメーションで構成されることが多く、予算が上がるほど表現の幅が広がります。
具体的には、以下のような項目が予算によって変動します。
- オリジナルのデザインやイラストをどこまで制作できるか
- アニメーションの滑らかさ・演出のリッチさ
- ナレーションやBGMの有無・クオリティ
- 制作前の構成・絵コンテのレベル感
- 修正対応の回数や対応スピード
「必要最低限の伝わる動画」であれば30〜50万円前後、
「ブランド感や説得力を高めたクオリティ」を求めるなら100〜200万円以上の予算を見ておくとよいでしょう。
また、予算ごとのクオリティについてはこちらの記事をご参考ください。

スケジュールによって変わること
スケジュールも制作内容に大きく影響します。
制作期間が1ヶ月しか取れない場合と、2〜3ヶ月かけられる場合とでは、練り込める構成や修正対応の柔軟さがまったく異なります。
短納期でも制作は可能ですが、
- 制作側のスケジュール確保のため追加コストが発生する
- 修正に使える時間が限られる
- 事前準備が不十分だと、認識のズレが出やすい
といったリスクもあるため、可能な限り早めに動き出すのがおすすめです。
あらかじめ社内でも確認しておきたいこと
- 予算感(想定上限・社内で決裁が必要な金額帯)
- 希望納期(イベントやLP公開など、固定の締切があるか)
- 誰がOKを出すのか(決裁者・ステークホルダーは誰か)
これらが不明確なまま進めると、途中で方針が揺らいだり、社内での承認が取れずに遅延することもあります。
「どこまで準備できるか?」を冷静に整理しておくことで、制作のスピードと納得感が格段に変わります。
最後に
サービス紹介動画は、サービスの信頼性を高め、営業・マーケティングにおいて強力なツールとなります。しかし、制作のプロセスを誤ると、効果が半減してしまう可能性があります。
本記事で紹介した「失敗しないためのポイント」を押さえ、効果的な工場紹介動画を制作しましょう。
情報整理や予算の検討などの事前準備がご不安な方は筆者がお手伝いいたします。
是非、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。