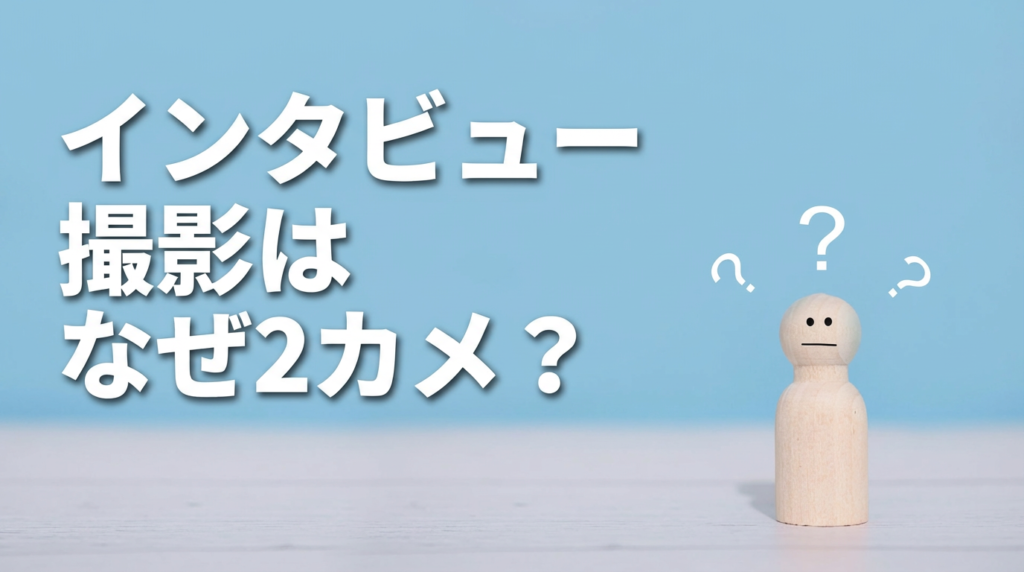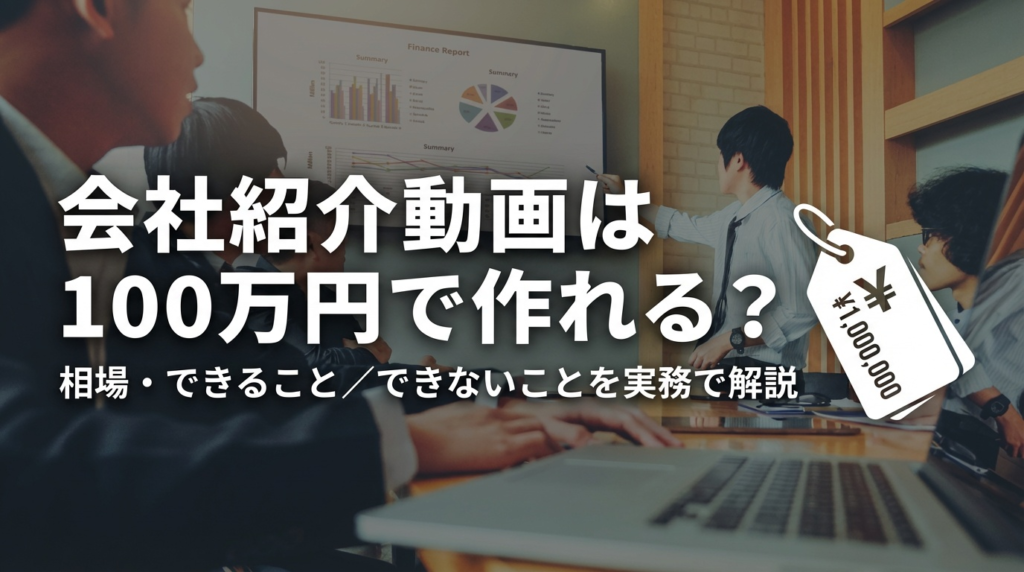「会期まで、あと6週間。動画は必要だけど、社内の承認はどう回す?撮影は本当にやる?——」余裕をもってスタートしたはずの展示会の準備は、なぜかいつも慌ただしくなりがちです。
この記事は、展示会向けの動画を制作するためのスケジュールとして、“理想論”でなく現実に回る進め方にこだわりました。
ぜひご一読いただき、これからの動画制作の参考にしてください。
この記事の要点
- 結論:展示会動画の標準的な制作期間は約6~8週間。ただし、これは発注側の協力と迅速な意思決定が前提。
- 目安:短納期なら約4週間、既存素材を活用した特急対応なら約2週間でも可能だが、相応の制約と追加コストが発生する。
- 注意点:最も遅延しやすいのは「承認・修正」工程。事前に関係者を絞り、フィードバックのルールを明確化することが成功の鍵。
- 次の一歩:まずは「会期日から逆算したスケジュール表」で全体像を把握し、動画の目的を明確にすることから始めましょう。詳しくは展示会動画の目的設計ガイドで解説しています。
制作期間の結論と全体像(標準・短納期・特急の3モデル)
展示会動画の制作期間は、動画の内容や制作体制によって大きく変動します。ここでは、典型的な3つのモデルを提示し、それぞれの前提条件や注意点を解説します。
| モデル | 期間 | 前提条件 | クリティカルパス | 修正回数目安 |
|---|---|---|---|---|
| 標準モデル | 約8週間 | 企画から丁寧に進行。関係者との合意形成を重視。 | 構成案のFIX、初稿の承認 | 2回 |
| 短納期モデル | 約4週間 | 承認者2名以内、48時間以内のFB、修正指示は1回に集約。 | 素材提供、初稿承認 | 1〜2回 |
| 特急モデル | 約2週間 | 既存アセットの活用、撮影なし、修正は軽微なもの1回のみ。 | 素材提供、構成FIX | 1回 |
標準モデル(約8週間)— 品質とスケジュールのバランス重視
品質を担保しつつ、現実的なスケジュールで進行する最も一般的なモデルです。企画から撮影、編集、修正まで、各工程で十分な時間を確保します。
W1〜2は「目的・KPI・サイネージ仕様」を握り切る期間。W3〜4でデザイン/編集の仮組み、W5で初稿、W6〜7で修正、W8で実機テストと最終チェック。“最初の2週で迷いを潰す”ほど、後ろの修正が軽くなります。
短納期モデル(約4週間)— 迅速な意思決定が必須
「出展まで時間がないが、クオリティは妥協したくない」という場合に選択されるモデル。発注側の協力体制と、迅速なフィードバックが成功の鍵となります。
W1に構成とメッセージを一気に確定。W2で初稿、W3で修正、W4で納品&実機。承認者は2名以内/48時間以内のフィードバック固定が鉄則。“悩みは会議ではなく原稿に書く”が合言葉です。
特急モデル(約2週間)— 既存アセット活用が前提
緊急対応のモデル。新規撮影は行わず、既存の動画素材や3DCG、Webサイトの画像などを最大限に活用して制作します。
撮影は原則なし。既存のBロール・3DCG・製品画像を棚卸しして即日共有。Day3で初稿、Day5で修正、Day10で書き出し・実機。“完璧より完了”の判断軸を共通言語に。
展示会向け動画制作における、工程詳細と役割分担(発注側/制作会社/施工会社)

企画・要件定義(目的/KPI/サイネージ仕様FIX)
このフェーズが最も重要です。動画の目的(集客、滞留、商談化)を明確にし、KPI、動画の役割を設定します。また、展示ブースの施工会社と連携し、サイネージ・ディスプレイの位置を確定させます。
素材準備/撮影/制作(MG/実写)
企画内容に基づき、モーショングラフィックス(MG)や実写撮影を行います。発注側は、製品の3DCGデータやロゴデータ、既存の動画素材などを速やかに提供する必要があります。
レビュー・修正(初稿→2稿→最終/修正ルール)
制作会社から提出された初稿に対し、フィードバックを行います。修正指示は、関係者の意見を集約し、担当者が一元化して伝えることが重要です。
書き出し・実機テスト・納品
最終版の動画を、サイネージの仕様に合わせて書き出します。納品後は、必ず展示会本番で使用する機材で再生テストを行い、問題がないかを確認します。
週次ガントチャート(サンプル表)
ここでは、標準的な「8週間モデル」のガントチャートをサンプルとして示します。タスクの依存関係と担当者を明確にすることが、プロジェクト成功の第一歩です。
8週間モデル(WBS × 週次タスク × 担当)
| WBS | タスク | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.企画 | 目的/KPI設定、仕様FIX | ● | 発注/制作 | |||||||
| 1.企画 | 構成案/絵コンテ作成 | ● | 制作 | |||||||
| 1.企画 | 構成案FIX | ● | 発注側 | |||||||
| 2.制作 | 素材準備/提供 | ● | 発注側 | |||||||
| 2.制作 | デザイン/編集 | ● | ● | 制作 | ||||||
| 2.制作 | 初稿提出 | ● | 制作 | |||||||
| 3.修正 | 初稿レビュー | ● | 発注側 | |||||||
| 3.修正 | 2稿制作 | ● | 制作 | |||||||
| 3.修正 | 2稿レビュー | ● | 発注側 | |||||||
| 4.納品 | 最終版制作 | ● | 制作 | |||||||
| 4.納品 | 実機テスト | ● | 発注/施工 |
4週間モデル(短縮の要点)
4週間モデルでは、各工程を並行して進める必要があります。例えば、W1で構成案を作成しつつ、発注側はW2の素材準備を前倒しで進めます。レビュー期間も各3日以内に限定するなど、タイトな進行が求められます。
| WBS | タスク | W1 | W2 | W3 | W4 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.企画 | 目的/KPI設定、仕様FIX | ● | 発注/制作 | |||
| 1.企画 | 構成案/絵コンテ作成 | ● | 制作 | |||
| 1.企画 | 構成案FIX | ● | 発注側 | |||
| 2.制作 | 素材準備/提供 | ● | 発注側 | |||
| 2.制作 | デザイン/編集 | ● | ● | 制作 | ||
| 2.制作 | 初稿提出 | ● | 制作 | |||
| 3.修正 | 初稿レビュー | ● | 発注側 | |||
| 4.納品 | 最終版制作 | ● | 制作 | |||
| 4.納品 | 実機テスト | ● | 発注/施工 |
2週間モデル(制約と割り切り)
2週間モデルは、実質的に「編集・修正」のみの工程です。W1前半で既存アセットを支給し、構成をFIX。W1後半で初稿を提出し、即日レビュー。W2で修正と納品を完了させます。品質よりも「間に合わせること」が最優先されます。
| WBS | タスク | W1 | W2 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 1.企画 | 目的/KPI設定、仕様FIX | ● | 発注側 | |
| 1.企画 | 構成案/絵コンテ作成 | ● | 発注側 | |
| 1.企画 | 構成案FIX | ● | 発注側 | |
| 2.制作 | 素材準備/提供 | ● | 発注側 | |
| 2.制作 | デザイン/編集 | ● | 制作 | |
| 2.制作 | 初稿提出 | ● | 制作 | |
| 3.修正 | 初稿レビュー | ● | 発注側 | |
| 4.納品 | 最終版制作 | ● | 制作 | |
| 4.納品 | 実機テスト | ● | 発注/施工 |
ミニケース:実際に2週間で間に合わせた手順
- Day1(午前):既存素材を共有(過去動画・Web画像・3DCG・ロゴ・フォント)。不足は「代替案」を即決。
- Day1(午後):15/30/60秒の3尺で構成骨子を確定(テロップ文言までテキスト化)。
- Day3:初稿提出。テロップ・尺・差し替え素材だけにFBを限定。
- Day5:修正版提出。H.264/MP4で一旦書き出し、実機でジャギー/黒み/ループ継ぎ目を確認。
- Day7〜10:最終版→サイネージで通し再生テスト。USB×2/クラウドでバックアップ。
承認・修正を遅延させない仕組み
プロジェクトの遅延原因の9割は、承認・修正工程にあります。これを防ぐための実務的な仕組みを3つ紹介します。
承認者の集約 / FB様式(テキスト一元化)
最終承認者を事前に1〜2名に絞り込みます。関係各所からのフィードバックは、必ずプロジェクト担当者がExcelやスプレッドシートに集約し、制作会社には一本化されたテキスト情報として渡すルールを徹底します。
修正回数と範囲の合意
キックオフの段階で、「初稿提出後の修正は2回まで」のように、修正回数と、その範囲(例:テロップ修正は可、構成変更は不可)を明確に合意しておきます。これにより、無限の修正ループやスコープ外の要求を防ぎます。
バッファ設定(全体の10〜20%)
どれだけ緻密な計画を立てても、不測の事態は起こり得ます。全体のスケジュールに対し、10〜20%程度のバッファ(予備日)を設けておくことで、軽微な遅れを吸収し、最終的な納期遵守の確度を高めます。
会期日からの逆算テンプレ
展示会動画のプロジェクトは、会期日から逆算して計画を立てるのが鉄則です。以下に、標準的な8週間モデルをベースにした逆算チェックリストを記載します。
- T-56(8週間前):制作会社へ打診、オリエンテーション実施。目的・予算・KPIのすり合わせ。
- T-28(4週間前):構成案・絵コンテFIX。撮影が必要な場合はこの時期までに完了。編集作業が本格化。
- T-14(2週間前):初稿レビューとフィードバック。修正指示を一元化して提出。
- T-7(1週間前):最終版の動画データ納品。
- T-1(前日):展示会場での設営。実機での最終再生テスト。バックアップの確認。
- 当日:安定したループ再生を確認。ブーススタッフへの操作説明。
- 会期後:お礼メールでの動画活用、Webサイトへのアーカイブ掲載。
今すぐできる次の一歩:テンプレに会期を入れてWBSを自動計算 → 承認者2名・FB締切48時間を会議体で先に合意 → サイネージ・ディスプレイの位置を確認。ここまでで遅延の8割は防げます。
テンプレ(8週/4週/2週のWBS・FB集約シート)が必要でしたら、こちらから無料でお送りします。
無料テンプレートが必要な方はこちらよりお問い合わせください。
短納期で間に合わせるテクニック

「どうしても時間がない」という状況でも、諦めるのはまだ早いです。ここでは、短納期を実現するための3つの実践的なテクニックを紹介します。詳細は短納期で間に合わせる工程設計の記事でも解説しています。
既存アセット流用(3DCG/過去動画/Web画像)
最も効果的な時間短縮方法は、新規の素材制作をゼロにすることです。製品紹介サイトの画像、過去の動画のBロール、製品の3DCGデータなど、手持ちの資産を棚卸ししましょう。これらを組み合わせるだけでも、十分に魅力的な動画は制作可能です。
デザインテンプレートや購入素材の活用
多くの制作会社は、過去に制作したデザインのテンプレートを保有しています。また、購入素材を活用することで、企画・デザイン工程を大幅に圧縮できます。
撮影を行う最小構成(半日×1・インタビュー中心)
どうしても実写が必要な場合は、撮影規模を最小限に抑えます。例えば、撮影を「半日×1回」に限定し、製品のデモや開発者インタビューなど、要点を絞った撮影に集中します。これにより、撮影準備やロケハンにかかる時間を削減できます。
納品仕様と実機検証(落とし穴集)
動画データが完成しても、それが展示会場で正しく再生されなければ意味がありません。ここでは、納品ファイルの仕様や、現場での再生テストにおける「落とし穴」を解説します。
推奨出力(MP4/H.264/AAC/1920×1080・10〜20Mbps)
最も汎用性が高く、トラブルが少ない納品仕様は以下の通りです。制作会社に依頼する際は、この仕様をベースに、使用するサイネージのスペックに合わせて調整してもらいましょう。
| 項目 | 推奨仕様 | ポイント |
|---|---|---|
| ファイル形式 | MP4 | 最も汎用性が高いコンテナ形式。 |
| 映像コーデック | H.264/AVC | 圧縮率と画質のバランスに優れる標準的なコーデック。 |
| 音声コーデック | AAC | 無音動画でも音声トラックを含んだ形式が一般的。 |
| 解像度 | 1920×1080 | フルHD。縦型サイネージの場合は1080×1920。 |
| ビットレート | 10〜20Mbps | 画質とファイルサイズのバランスが良い。これより低いと画質が荒れる可能性。 |
推奨納品仕様チェック表 ループ設定/無音前提/輝度・コントラスト
展示会動画特有の注意点です。
動画の最初と最後を自然につなぎ、ループ再生時に違和感がないように編集します。
また、無音で再生されることを前提に、テロップやグラフィックだけでも情報が伝わるように設計します。会場の照明は明るいため、PC画面で見るよりも輝度やコントラストを若干高めに設定すると、視認性が向上します。
当日トラブル対策(バックアップ/電源/簡易マニュアル)
- バックアップ:動画ファイルを入れたUSBメモリを複数本用意。再生用PCも予備機があると万全。
- 電源管理:PCのスリープモードやスクリーンセーバーは全てOFFに。電源ケーブルが抜けないよう、養生テープで固定。
- 簡易マニュアル:再生手順やトラブルシューティングをまとめたA4一枚程度のマニュアルを用意し、ブーススタッフ全員が対応できるようにしておく。
よくある質問

- 展示会動画の制作期間はどのくらい?
-
標準的な制作期間は約6~8週間です。ただし、これは発注側の協力と迅速な意思決定が前提となります。短納期の場合は約4週間、既存素材を活用した特急対応なら約2週間でも可能ですが、相応の制約と追加コストが発生します。
- 制作スケジュールが遅延する最も多い原因は?
-
最も多い原因は「承認・修正」工程の遅延です。関係者の意見調整に時間がかかったり、後からスコープ外の修正要求が出たりすることで、スケジュールが大幅に圧迫されるケースが後を絶ちません。
- 会期まで1ヶ月を切ってしまった場合、どうすればいい?
-
まずは制作会社に相談しましょう。既存の動画素材や製品の3DCGデータ、Webサイトの画像などを活用する「特急モデル」であれば、約2週間での制作も可能です。品質よりも「間に合わせること」を最優先とした進行となります。
- 制作会社への見積もり依頼はいつ頃がいい?
-
会期の3ヶ月前、遅くとも2ヶ月前には依頼するのが理想的です。複数の会社から見積もりを取り、比較検討する時間を考慮すると、早めに動き出すに越したことはありません。
- ブース施工会社と制作会社、どちらに先に相談すべき?
-
両者に同時並行で相談するのがベストです。動画の仕様はブースの設計に、ブースの設計は動画の見せ方に影響するため、三者間で情報を密に連携させながら進めるのが成功の鍵です。
まとめ:成功するスケジュール管理チェックリスト
- 動画の目的(集客/滞留/商談化)は明確か?
- 会期日から逆算したスケジュールを立てているか?
- サイネージの仕様(解像度/比率/輝度)は確定しているか?
- 承認者は1〜2名に絞られているか?
- 修正回数と範囲のルールは合意できているか?
- 全体の10〜20%のバッファを確保しているか?
- 実機での再生テストは計画されているか?
これらのポイントを押さえ、計画的にプロジェクトを進めることが、展示会動画を成功に導く鍵となります。より詳細な戦略については、展示会動画の目的設計ガイドも併せてご覧ください。
情報整理や予算の検討などの事前準備がご不安な方は筆者がお手伝いいたします。
是非、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。