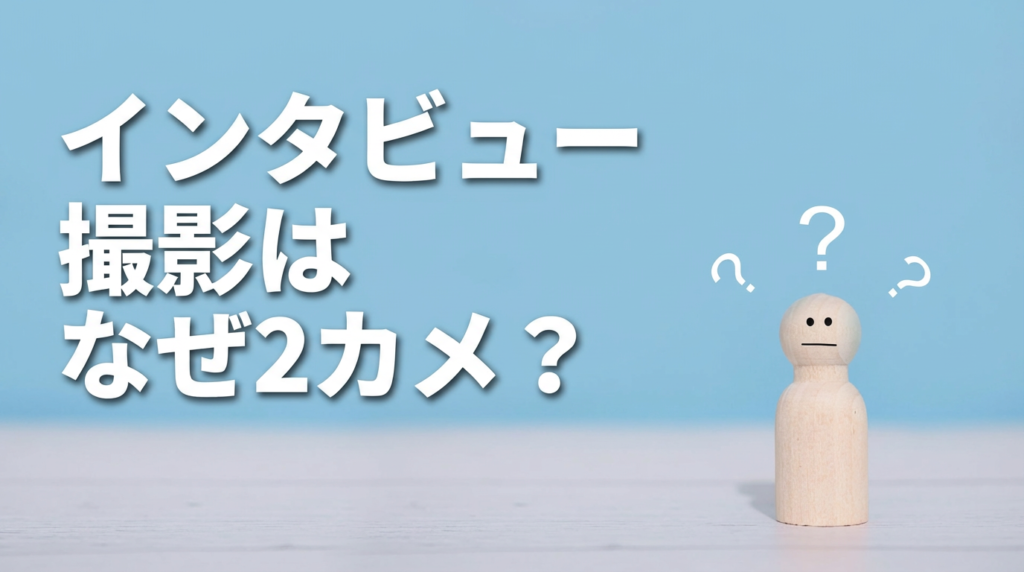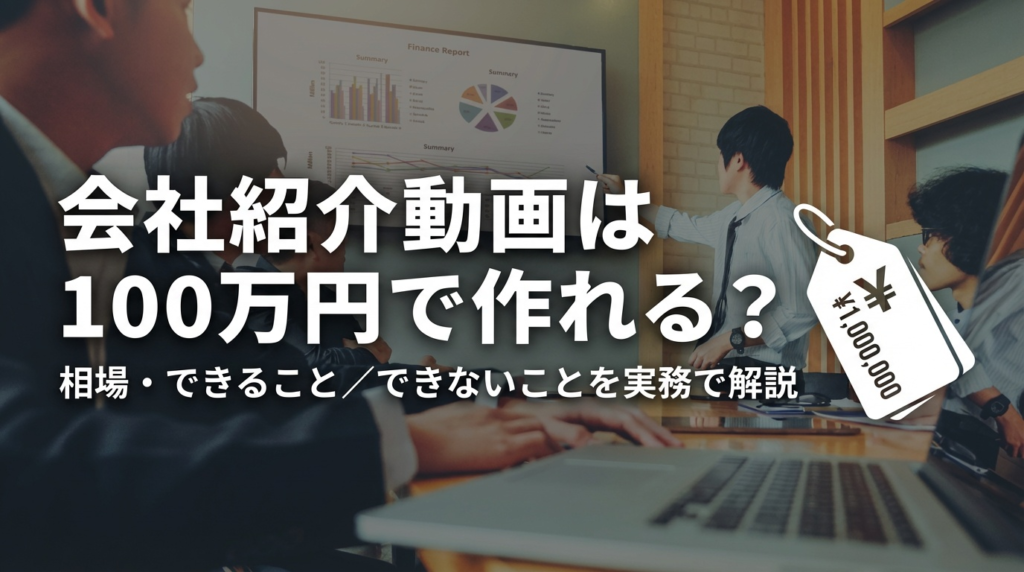会社紹介動画を活用する企業が、近年ますます増えています。
その背景には、採用活動や営業、株主向けの情報開示など、企業が「どんな会社なのか」を伝える場面が急増していることがあります。さらに、テレワークやオンライン面接の普及、展示会のオンライン化などによって、対面の場で直接“社風”や“雰囲気”を伝える機会が減ってきたことも、大きな要因です。
会社紹介動画は、誰に、何を、どのように伝えるかによって、構成や撮影内容、編集方針が大きく変わるコンテンツです。
そのため、目的を整理しないまま「とりあえず動画をつくる」といった進め方では、本来伝えたかったことがぼやけてしまい、期待した効果が得られないケースも少なくありません。
この記事では、会社紹介動画の活用シーンや、予算別にできることの違い、そして発注前に確認しておきたいチェックポイントについて、プロの視点からわかりやすく解説していきます。
筆者のプロフィール
まず、この記事を読んでいただくにあたって「誰が何を書いているのか?」も非常に重要な要素になると思いますので、簡単に私のプロフィールをまとめています。

【株式会社case 代表取締役/動画制作プロデューサー:加藤智史】
新卒で入社した動画制作会社で広告・マーケティング・採用・人材研修など約400本の動画制作に携わる。その後、TVCMなどの制作を行う、大手制作会社にアカウントエグゼクティブとしてジョイン。数千万円規模のプロモーション案件に携わり、動画にとどまらないクリエイティブ制作やプロジェクトマネジメントを経験。現在は本メディアの運営を通じた企業動画の受託制作や、動画制作会社の営業支援などを行う。
動画制作会社(予算数十万円〜数百万円)での営業兼プロデューサーとしての役割を中心に、広告代理店(予算数百万円〜数千万円)でのアカウント(クライアントと社内クリエイティブチームの窓口、PM業務を担当する役割)なども経験しているため、比較的高い説得力で本記事をお届けできるのではないかと考えています。
1. 会社紹介動画の主な活用シーン
会社紹介動画とひとことで言っても、目的や視聴者によって、その活用シーンはさまざまです。制作する際には、どのシーンで誰に向けて使うのかを明確にすることで、構成やトンマナ(トーン&マナー)を適切に設計することができます。ここでは、代表的な活用シーンを4つ紹介します。
採用活動(新卒・中途)
近年もっとも需要が高まっているのが採用領域での活用です。
特にオンライン採用が進む中で、社内の雰囲気や働く社員の姿、オフィスの環境などを動画で伝えることで、求職者に「ここで働く自分」をイメージさせやすくなります。
活用例:
- 採用サイトへの掲載
- 説明会・面接時の冒頭で上映
- リファラル採用用に社員がSNS等で共有
営業・商談の場面
展示会や商談、提案資料などで会社紹介動画を活用する企業も増えています。
単なる会社概要資料では伝えきれない、企業の姿勢や雰囲気を“温度感のある表現”で届けられるのが、動画の大きな強みです。
特に、グローバルに事業を展開している企業が、海外のクライアントに自社を紹介する場面では、言語や文化の壁を越えて直感的に伝わる「会社紹介動画」は非常に有効です。字幕やナレーションを多言語対応にすることで、現地営業の支援ツールとしても活用できます。
活用例:
- 展示会のモニター再生
- 提案資料に埋め込み
- 商談時のアイスブレイクとして上映
株主・投資家向けのIR・会社説明
企業としての透明性や信頼性を示す目的で、IR用途の会社紹介動画を制作するケースもあります。
事業内容だけでなく、沿革や将来の展望をビジュアルで伝えることで、理解促進や印象向上に寄与します。
活用例:
- 株主総会や決算説明会での活用
- 会社案内のデジタル化
自社サイトや採用メディアなどのオンライン掲載
オウンドメディアや求人媒体での露出も、動画ならではの効果が発揮されます。
「読まれない」「スクロールされない」といったWebコンテンツの課題を補い、視覚的に“企業らしさ”を伝える手段として有効です。
2.会社紹介動画の制作費用の目安と予算別の事例
会社紹介動画を制作する際に、一番気になるのは「いくら必要なのか?」ということでしょう。「動画はとても高い」というイメージをお持ちの方も非常に多いのですが実はWebサイトや紙のパンフレットと比較してものすごく高いということはなく、むしろ安く制作することも可能です。
あくまでも参考値ですが目安としては、
- 50−80万円:会社紹介動画を制作する上で最低限必要な予算
- 100−150万円:潤沢ではないが、情報量・見た目のクオリティを担保できる予算
- 150−200万円:情報量はもちろん、見た目でも違いを出せる予算
- 250万円〜:特殊な制作条件や3DCGの活用などにも対応可能な予算
このようなイメージを持って頂けると、おそらく他社との商談の際にも大きく予算感が乖離することはないでしょう。
具体的に予算別の事例を見ていきます。
※あくまでも弊社であれば…という事例になりますので、ご留意ください。
50−80万円
100−150万円
150−200万円
250万円〜
4.動画制作の外注に失敗しないための4つのポイント
動画制作を外注した経験のある人の中には、なんらかの理由で「失敗した」「上手くいかなかった」と感じている方がいます。筆者もお客様からそのような相談を受けたことが何度かあります。
詳細は下記の記事にまとめていますが、ここでは失敗しないために重要な4つのポイントをご紹介します。

適切な制作会社を選ぶ
もちろん発注側としてもそれを強く望んでいると思いますが、
ここで端的にお伝えしたいのは、「信頼できる営業担当者を選ぶ」という視点をもってみることです。
筆者が動画制作に携わり始めた10年ほど前とくらべると動画制作会社は格段に増えました。そしてどの会社も甲乙つけがたいほど豊富な制作実績を持っています。(弊社はまだ会社としての実績は少ないですが…)
その中で何をポイントに選ぶか?の1つのポイントが上記の「信頼できる営業担当者を選ぶ」という視点です。
詳しくは下記の記事にまとめていますが、端的にお伝えすると、

- 優秀な営業担当は、優秀なプロデューサー、優秀なクリエイターをアサインできる
- 優秀な営業担当は、無用なトラブルを避けてくれる
- 優秀な営業担当は、コミュニケーションがスムーズ
という3点です。「絶対この会社がいい!」と思える会社が見つからず悩むことがあればぜひ参考にしてみてください。
そしてもし悩むようであれば、ぜひ筆者にもご相談ください。
スケジュールに余裕を持つ
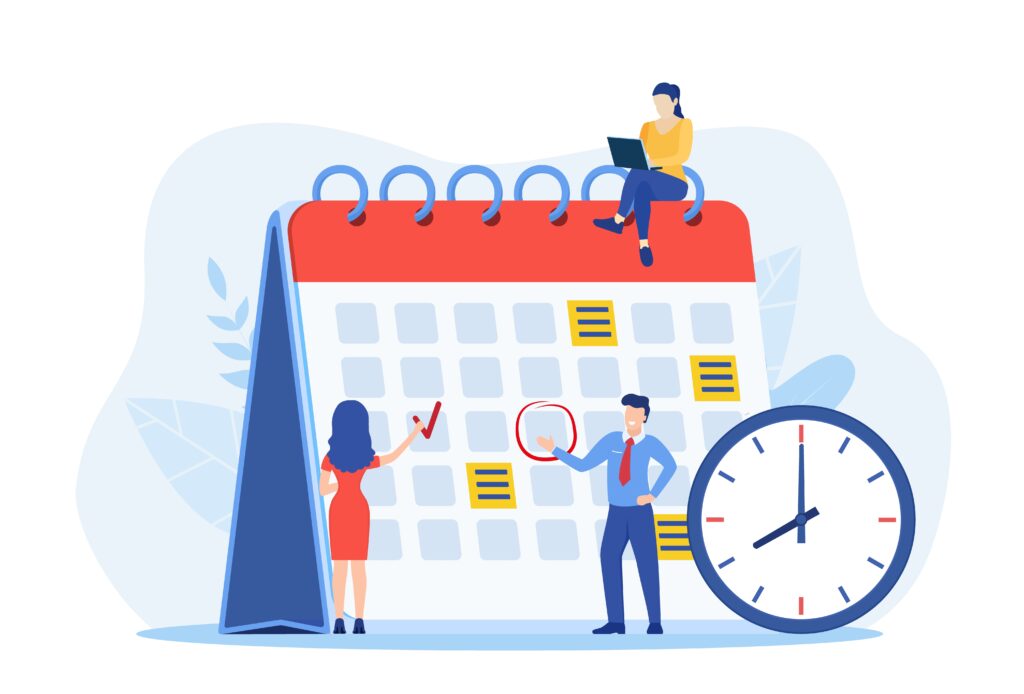
基本的なことではありますが、何らかの理由で急いで制作を進めなければならないケースもあります。そのような場合、
- 人的なリソースを確保するために通常スケジュールでの進行よりもお金がかかる
- 急ぐ分、準備・確認に通常より時間を割くことができず何らかのトラブルが起きる可能性が高くなる
…というリスクがあります。
会社によっては、短納期でも費用を抑えて制作してくれる会社もあるかもしれませんがそれでもスケジュールを短縮するということは、どこかでなにかを犠牲にせざるを得ません。
もちろん、通常スケジュールよりもトラブルが起きる可能性が高まるというだけで、「必ずトラブルになる」「失敗する」わけではありません。制作に慣れているプロが進行する以上、トラブルの種は極力排除し最大限問題なく進行できるよう尽力することは間違いありません。
ただ、それでも想定外のトラブルに見舞われることもあるのが動画をはじめ、クリエイティブ制作の現場です。
だからこそ、できる限りスケジュールには余裕を持つことを強くおすすめします。
制作内容によって変動しますが、会社紹介動画であれば、最低2ヶ月。できれば3ヶ月ほど制作スケジュールが確保できると良いでしょう。
上記はあくまでも「制作期間」なので、制作会社を選んだり正式に発注するまでのリードタイムがどれくらい必要になるかについては、自社の稟議や予算申請のフローについて事前に把握しておく必要があります。
完成イメージをできるだけ具体的にする
いざ、動画制作をスタートする際には制作会社側からどのような動画が完成する予定であるかは絵コンテやシナリオなどの資料を用いて説明があるはずです。
動画制作に慣れていれば、そのような資料で具体的なイメージを持つことができますが、初めての場合にはそれでもイメージが難しいこともあるでしょう。
そのような場合には、遠慮なく制作会社側に質問してイメージの具体化に努めましょう。
制作過程で完成イメージの認識の相違などのズレが生じてしまうと、軌道修正には時間とコストがかかってしまいます。
社内調整を怠らない
発注側の企業の担当者の方の役割の1つが、自社内のステークホルダーとの共通認識の形成です。
- こんな目的でこんな動画を制作します。
- これが完成イメージです。
- いつころ完成予定です。
- このタイミングでシナリオや動画を確認して、いつまでにフィードバックしなければなりません
…などなど、動画制作の背景や前提、クリエイティブイメージ、スケジュールなどについて関係者としっかりと「握る」ことができていないと、後になって「どんでん返し」が起きることは珍しいことではありません。
特に、動画制作について最終的なOKを出せる決裁権者とのすり合わせは重要です。
まとめ|“相談できる会社”をパートナーに
ここまで、東京で動画制作会社を選ぶ際に見ておきたい5つの視点をご紹介してきました。
どれも当たり前のように見えるかもしれませんが、実際の制作現場では「気づかないまま選んでしまった」という声を多く耳にします。
動画制作は、完成までにさまざまな確認や調整が発生するプロジェクトです。
だからこそ、最終的に大切なのは「この人になら相談できる」「一緒に考えてもらえる」という信頼感です。
制作会社の規模や実績よりも、「誰が、どんな姿勢で向き合ってくれるのか?」を重視して選ぶことで、
目的に合った、納得のいく動画制作が実現できるはずです。
もし、「どう進めていいかわからない」「そもそも動画が必要かどうか悩んでいる」という段階でも大丈夫です。
caseでは、構成や制作に入る前の“企画段階”から丁寧にヒアリングを行い、
「そもそも、何をどんな目的で伝えるべきか?」から一緒に設計していくスタイルを大切にしています。
お気軽にご相談いただければ、状況に応じたベストな進め方をご提案いたします。
情報整理や予算の検討などの事前準備がご不安な方は筆者がお手伝いいたします。
是非、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。