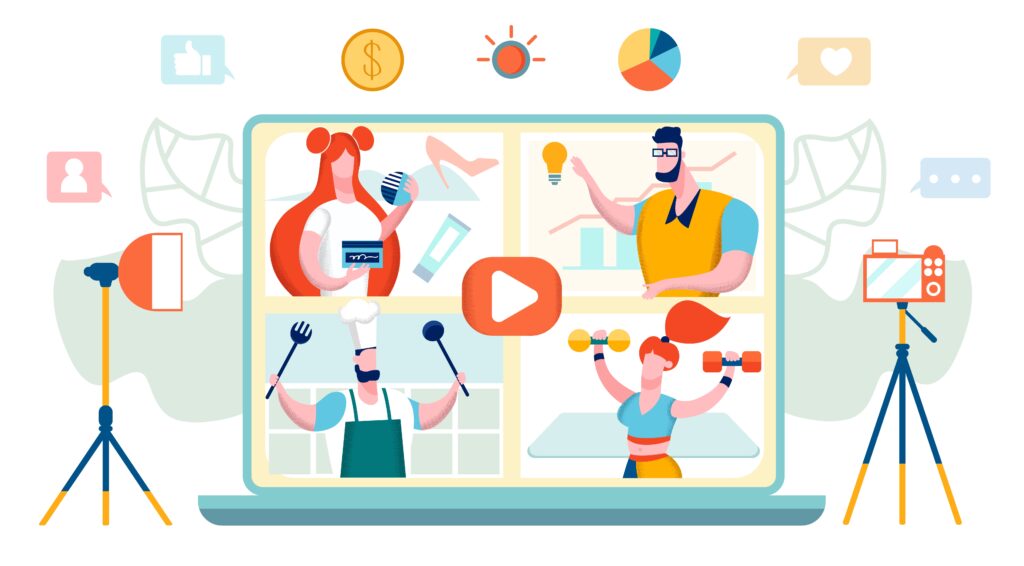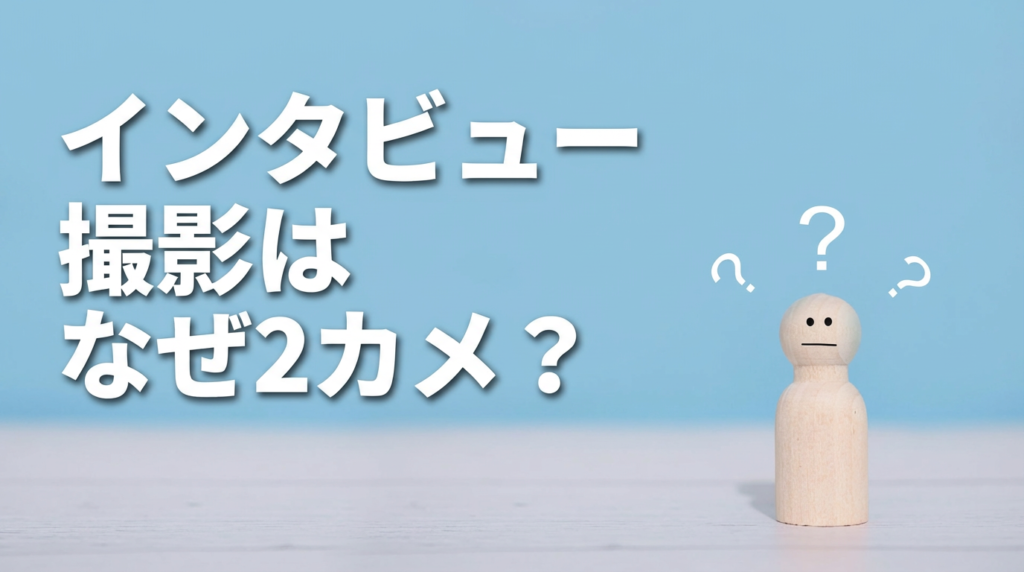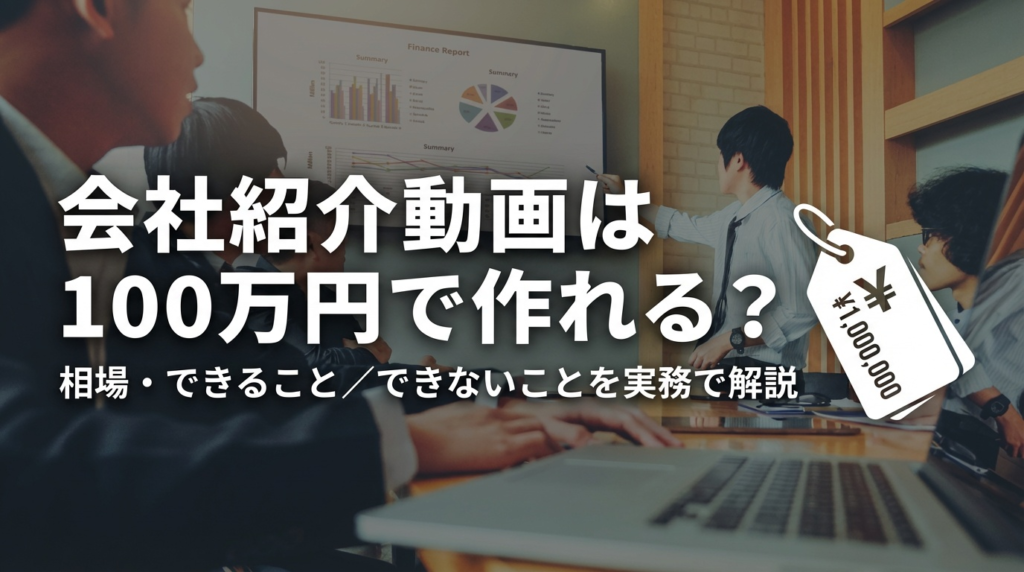動画制作は、企画や編集のクオリティももちろん大切ですが、実は「どの会社に発注するか」で結果の8割が決まる――
これは、私が数百本の動画制作に関わる中で、常に実感してきたことです。
特に東京都内には、大小さまざまな動画制作会社が存在しており、Web検索をすればいくつもの会社が候補に上がってきます。
しかし、見た目が似たようなWebサイト、豊富な実績、バラバラな見積もり金額…その中から本当に自社に合う会社を選ぶのは、想像以上に難しいものです。
なんとなく「安そう」「実績が多そう」で決めてしまい、あとから「イメージと違った」「社内調整が大変だった」など、
思わぬ落とし穴にはまってしまうケースも少なくありません。
だからこそ今回は、“動画制作のプロ目線”で、東京の動画制作会社を選ぶときに見ておくべき5つの視点を整理しました。
これから発注を検討している方にとって、判断のモヤモヤが少しでも晴れるきっかけになれば幸いです。
筆者のプロフィール
まず、この記事を読んでいただくにあたって「誰が何を書いているのか?」も非常に重要な要素になると思いますので、簡単に私のプロフィールをまとめています。

【株式会社case 代表取締役/動画制作プロデューサー:加藤智史】
新卒で入社した動画制作会社で広告・マーケティング・採用・人材研修など約400本の動画制作に携わる。その後、TVCMなどの制作を行う、大手制作会社にアカウントエグゼクティブとしてジョイン。数千万円規模のプロモーション案件に携わり、動画にとどまらないクリエイティブ制作やプロジェクトマネジメントを経験。現在は本メディアの運営を通じた企業動画の受託制作や、動画制作会社の営業支援などを行う。
動画制作会社(予算数十万円〜数百万円)での営業兼プロデューサーとしての役割を中心に、広告代理店(予算数百万円〜数千万円)でのアカウント(クライアントと社内クリエイティブチームの窓口、PM業務を担当する役割)なども経験しているため、比較的高い説得力で本記事をお届けできるのではないかと考えています。
1. 価格だけで判断しない
動画制作会社を比較するとき、まず注目しがちなのが「見積もり金額の違い」です。
同じような依頼内容でも、数十万円単位で差が出ることは珍しくありません。
しかし、経験者ほど知っているのが、“金額の大小=クオリティの高低”とは限らないということです。
制作費は「何を、どの範囲まで、どのように作るか」で決まります。
たとえば、
- 撮影の有無
- アニメーションやナレーションの有無
- 編集や修正の対応範囲
- 打ち合わせの頻度や制作体制の厚み
といった細かな条件や制作会社が想定している体制によって、見積もりは大きく変動します。
そのため、「この金額に何が含まれているか」が明示されていない見積もりには注意が必要です。
一見安く見えても「構成案は自社で用意してください」「修正は1回まで」など、あとから追加費用がかかるケースもあります。
逆に、やや高めに見える見積もりでも、構成作成から撮影、編集、納品までを一貫してサポートしてくれるなら、むしろ安心して任せられることもあります。
大切なのは“この金額で、どこまでやってもらえるのか”を理解すること。
見積もりを比較するときは、金額だけでなく「その中身と説明のわかりやすさ」にも注目してみてください。
2. 実績の“見せ方”に惑わされない
多くの動画制作会社は、自社のWebサイトや資料で「過去の実績」を紹介しています。
しかし、見た目が華やかな実績や有名企業の名前に引っ張られて、「ここなら間違いない」と判断してしまうのは少し危険です。
重要なのは、その実績が“どんな目的で、誰に向けて、どんな効果を狙って”制作されたのかという点です。
たとえば同じ動画でも、
- 採用向けに制作された動画
- サービス紹介を目的とした動画
…という2本の動画では構成も演出もまったく異なるのが当然です。
にもかかわらず、「綺麗に見えるかどうか」「有名企業の案件かどうか」だけを判断軸にしてしまうと、
自社の目的やターゲットに合わない会社を選んでしまう可能性があります。
また、見栄えのする動画が多い会社が、必ずしも「構成設計が上手い」「編集の対応が丁寧」「発注者と密に連携できる」とは限りません。
実績を見るときは“見た目の派手さ”ではなく、「目的と成果の文脈」で評価する意識が大切です。
もし気になる制作会社があれば、
「これはどんな目的で制作された動画ですか?」
「どのような意図や背景があって、このような企画になったのですか」
といった質問をしてみると、その制作会社の提案力を垣間見ることができるでしょう。
3. 誰が担当するかで決める
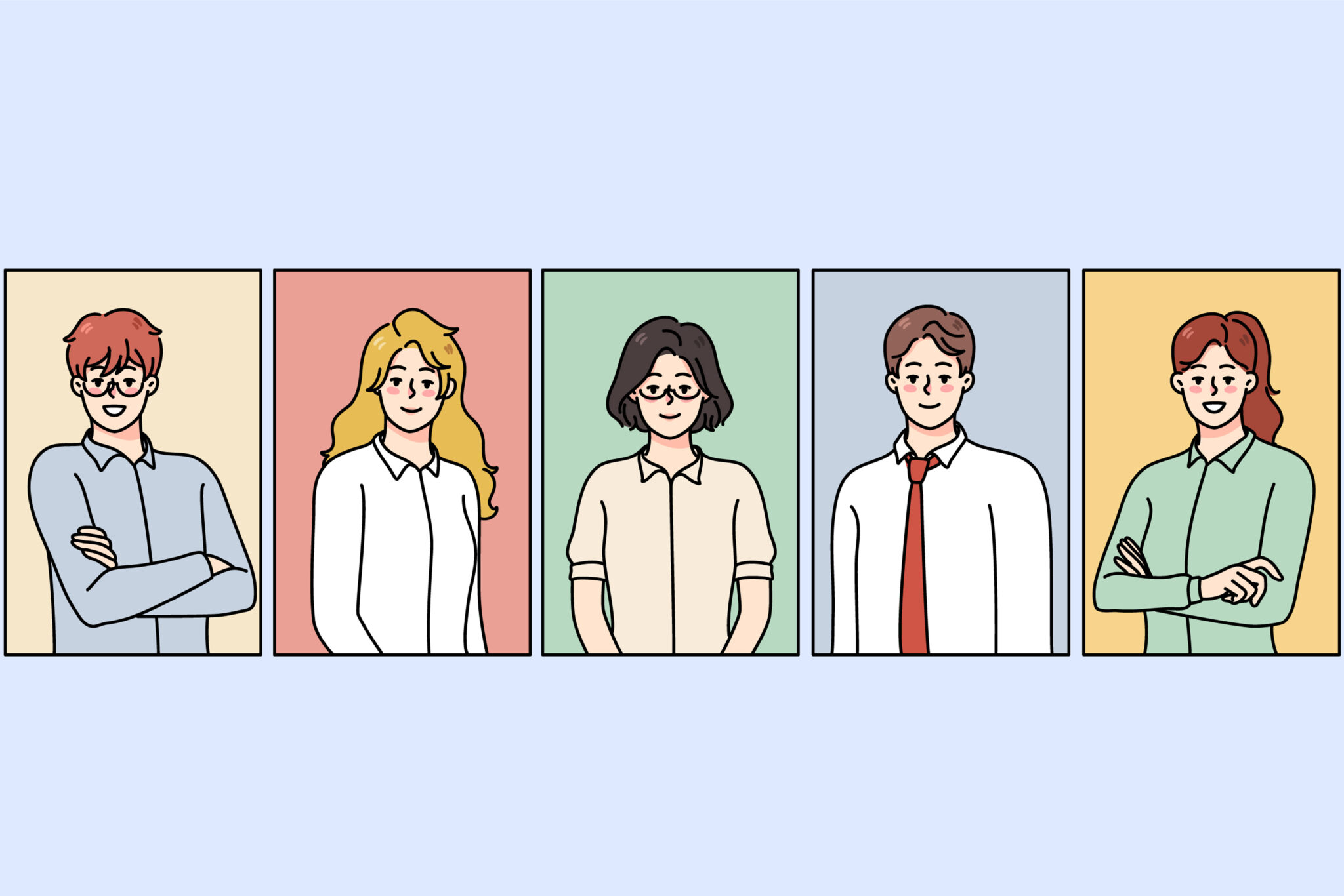
意外と見落とされがちですが、動画制作を進めるうえで“誰が担当につくか”は非常に重要です。
なぜなら、どんなに実績が豊富な制作会社であっても、実際にプロジェクトを動かすのは「担当者」だからです。
実際のやりとりや進行は、営業やプロデューサー、ディレクターといった担当者とのコミュニケーションで進んでいきます。
この担当者が、以下のような役割を担うことが多いためです。
- 課題や要望を正しく理解し、構成に落とし込む
- 社内メンバーや外部スタッフとの橋渡しをする
- スケジュールや修正対応の判断を行う
- 必要に応じて、表現方法や尺の調整などの提案を行う
つまり、担当者の「理解力・判断力・提案力」次第で、動画の方向性も進行のしやすさも大きく左右されるのです。
よくある失敗として、
「会社としては信頼できそうだったけど、担当者との会話がうまくかみ合わず、要望が伝わらなかった」
という声があります。これは、制作スキルの問題ではなく、コミュニケーションの設計や理解の深さに原因があるケースが多いです。
相談の段階で、
「こちらの話を噛み砕いてくれるか?」
「課題を整理しながら進めてくれるか?」
といった点を見極めることが、結果的に“いい動画”につながる近道になります。
動画制作の成功は、優秀な制作会社よりも、“信頼できる担当者との出会い”にかかっていると言っても過言ではありません。
👉 担当者選びの重要性について詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

4. 自社に合った提案をしてくれるか
動画制作の目的や活用方法は、企業によって大きく異なります。
にもかかわらず、あらかじめ用意されたテンプレートや「他社で好評だったから」という理由だけで提案されてしまうと、
本当に伝えたいことが抜け落ちたり、ターゲットに響かない動画になってしまう恐れがあります。
だからこそ重要なのは、「御社ならこういう見せ方が効果的だと思います」といった、自社に合った提案ができる制作会社かどうかです。
たとえば以下のような視点があると、提案の解像度が高いと判断できます。
- 活用シーン(LP掲載/展示会/SNSなど)に応じた構成の違いを説明してくれる
- ターゲットや業界特性を踏まえた表現のチューニングを提案してくれる
- 「何を伝えないか」も含めて情報整理してくれる
- 映像だけでなく、ナレーションやテロップの言葉選びにも気を配ってくれる
また、目的やゴールがまだ曖昧な段階でも、
ヒアリングを通じて「そもそも何を解決したいのか?」を一緒に考えてくれるかどうかも大切なポイントです。
提案力のある会社は、単に制作を請け負うだけではなく、企画の初期段階から「本当に必要な動画とは何か?」を共に模索してくれます。
予算や納期だけでなく、“どんな成果を目指すか”という視点で伴走してくれる会社こそ、信頼できるパートナーといえるでしょう。
5. 東京の強みをどう活かせるか
オンラインでのやり取りや全国対応が一般化した今、
「動画制作会社はどこにあっても同じでは?」と思う方もいるかもしれません。
たしかに、地方の制作会社やリモート対応のフリーランスに依頼する選択肢も増えています。
しかし、東京の動画制作会社だからこそ得られるメリットも、まだまだ多く存在します。
たとえば──
- 撮影の機動力が高い → 都内や近郊であれば、急な対応やロケハンもフットワーク軽く対応できる
- 対面での打ち合わせがしやすい → 複雑な企画や調整事項も、同席すればスピーディーに決まる
- 撮影・編集・演出など、各領域のプロが揃っている → 担当者の裁量で、最適なクリエイターをアサインできる柔軟性
- 大企業案件や業界横断の実績が多い → 多様な業種・規模の案件経験を活かした“引き出し”の多さ
特に、撮影を伴う動画制作では、地理的な距離がそのまま制作スピードや柔軟な対応力に直結することも少なくありません。
また、展示会・セミナー・発表会など、東京発信のビジネスイベントとの連動を前提に動画を作るケースも多いため、
“東京発”という制作体制が、そのまま成果につながる場面もあるのです。
「地元では難しい要望も、東京の制作会社なら実現できる」
そんな視点で、エリア性をひとつの選定基準にしてみるのも有効です。
まとめ|“相談できる会社”をパートナーに
ここまで、東京で動画制作会社を選ぶ際に見ておきたい5つの視点をご紹介してきました。
どれも当たり前のように見えるかもしれませんが、実際の制作現場では「気づかないまま選んでしまった」という声を多く耳にします。
動画制作は、完成までにさまざまな確認や調整が発生するプロジェクトです。
だからこそ、最終的に大切なのは「この人になら相談できる」「一緒に考えてもらえる」という信頼感です。
制作会社の規模や実績よりも、「誰が、どんな姿勢で向き合ってくれるのか?」を重視して選ぶことで、
目的に合った、納得のいく動画制作が実現できるはずです。
もし、「どう進めていいかわからない」「そもそも動画が必要かどうか悩んでいる」という段階でも大丈夫です。
caseでは、構成や制作に入る前の“企画段階”から丁寧にヒアリングを行い、
「そもそも、何をどんな目的で伝えるべきか?」から一緒に設計していくスタイルを大切にしています。
お気軽にご相談いただければ、状況に応じたベストな進め方をご提案いたします。
情報整理や予算の検討などの事前準備がご不安な方は筆者がお手伝いいたします。
是非、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。