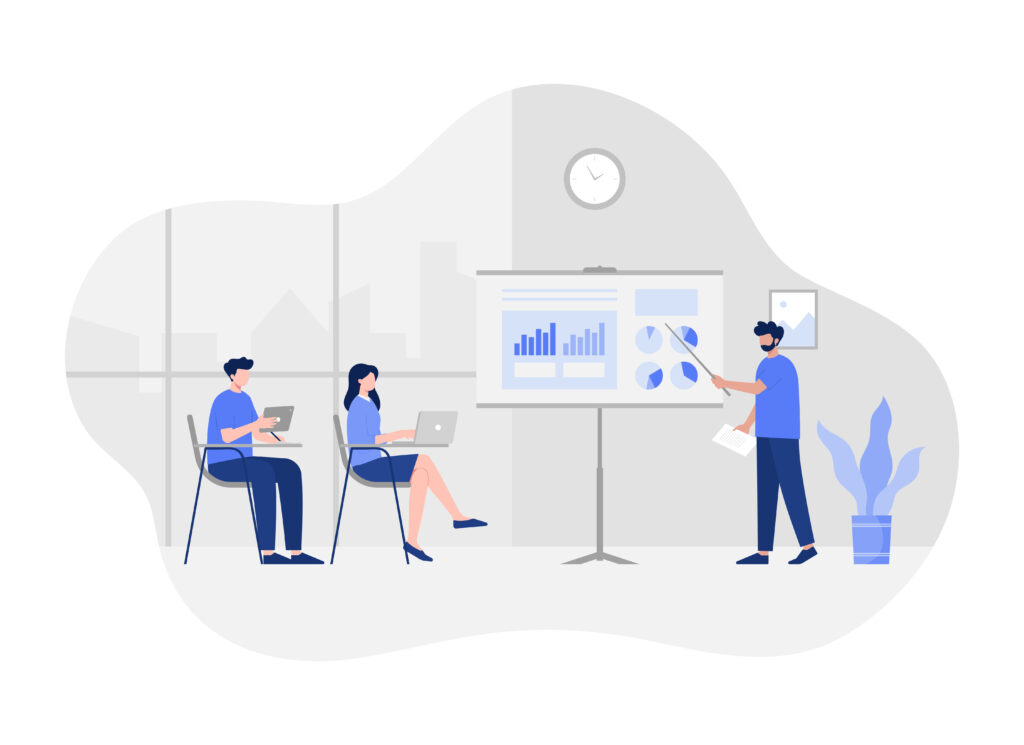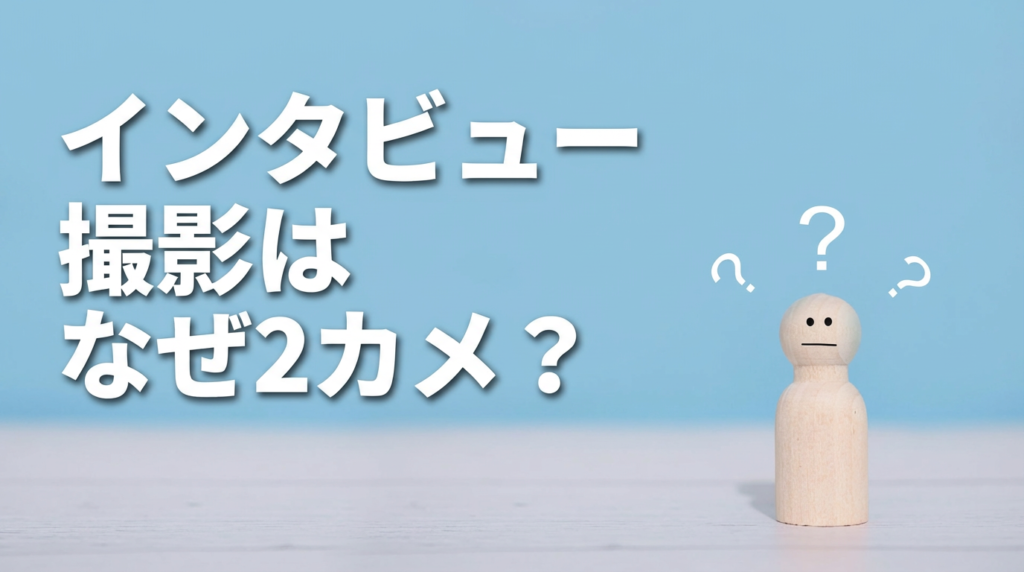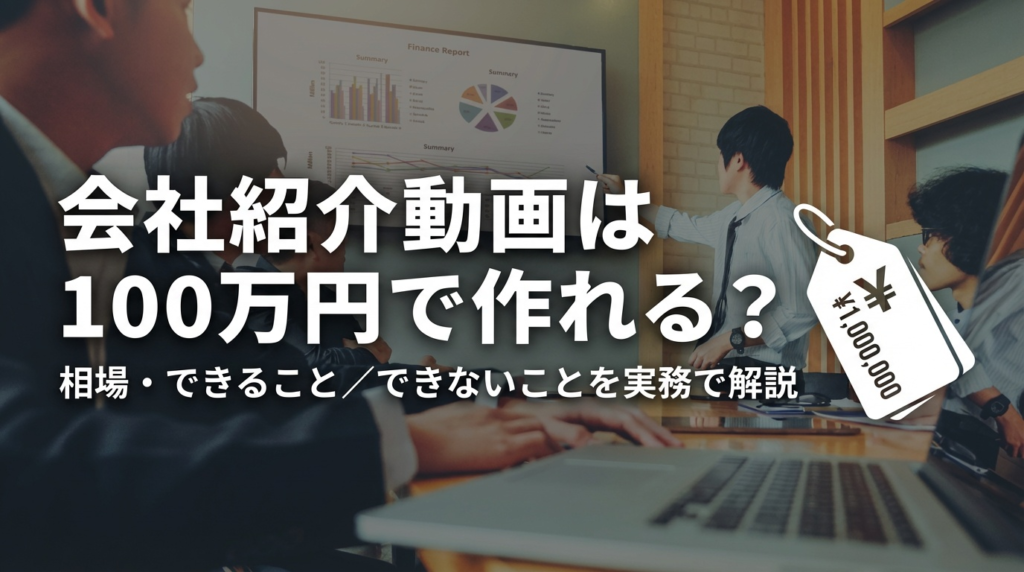現在、多くの企業が商品・サービスの認知や理解促進の手段として「動画」を活用しています。特に無形商材のプロモーションにおいては、目に見えにくい価値を可視化し、言葉では伝えきれない体験や機能を直感的に伝える手段として、アニメーションを用いたサービス紹介動画のニーズが高まっています。
本記事では、これまで数多くの動画を手がけてきた弊社の視点から、「サービス紹介動画」の活用方法や制作時の考え方、具体的な事例までを整理してご紹介します。
筆者のプロフィール
まず、この記事を読んでいただくにあたって「誰が何を書いているのか?」も非常に重要な要素になると思いますので、簡単に私のプロフィールをまとめています。

【株式会社case 代表取締役/動画制作プロデューサー:加藤智史】
新卒で入社した動画制作会社で広告・マーケティング・採用・人材研修など約400本の動画制作に携わる。その後、TVCMなどの制作を行う、大手制作会社にアカウントエグゼクティブとしてジョイン。数千万円規模のプロモーション案件に携わり、動画にとどまらないクリエイティブ制作やプロジェクトマネジメントを経験。現在は本メディアの運営を通じた企業動画の受託制作や、動画制作会社の営業支援などを行う。
動画制作会社(予算数十万円〜数百万円)での営業兼プロデューサーとしての役割を中心に、広告代理店(予算数百万円〜数千万円)でのアカウント(クライアントと社内クリエイティブチームの窓口、PM業務を担当する役割
なども経験しているため、比較的高い説得力で本記事をお届けできるのではないかと考えています。
なぜ今、サービス紹介動画が求められているのか?
スマートフォンと高速通信の普及により、動画は今や情報発信のスタンダードになりました。特にBtoB・BtoCを問わず、サービスやアプリケーションといった形のない商材において、文章や画像だけでは伝わりにくい魅力を視覚的かつ短時間で伝えることができるのが、動画の大きな強みです。
その中でも、アニメーションやモーショングラフィックスを活用したサービス紹介動画は、
- 実写よりも柔軟な表現が可能
- 世界観やコンセプトを自由に設計できる
- 制作コストのコントロールがしやすい
といった特長から、幅広い業種・業界で採用されています。
サービス紹介動画動画の活用方法
サービスの解説(理解促進)
マーケティングファネルにおける「理解促進」をゴールとした、動画尺30秒〜2分程度の比較的長めの尺であることが特徴です。
動画の構成としては、
- 課題や困りごとの提示
- そのサービスが解決策になることを提示
- サービスを活用するシーンやメリット・ベネフィット
- サービスの利用や導入が簡単・費用的な負担が少ないなど、ハードルの低さをアピール
という形で制作されることが多く、「この動画を見ればおおよそ理解できる」ような動画を制作されるケースもあれば、いずれかの訴求ポイントに絞られるケースもあります。
この点については後述する「制作の目的」によってあるべき動画の構成は変わるため、「制作のポイント」の章をお読み下さい。
コンセプト紹介
広告と違い、「対象となるものを一貫して、骨格となる発想や着眼点を動画で表現したもの」です。

「サービス紹介動画」を制作したいというニーズの中にコンセプト紹介を目的としたものが含まれるケースは少ないですが、発注側・制作会社側いずれも「〇〇動画」の〇〇の部分を明確に定義して言葉を使い分けられている…というわけでもないため、本記事では活用方法の1つとしてご紹介しています。
広告
ここでいう広告は「媒体・メディアに広告費・掲載費を支払って動画を配信すること」を指しています。マーケティングファネルにおける「認知拡大」を目的とし、動画の尺も15秒〜1分と比較的短いものが多いです。
また、サービス紹介動画を広告として活用する場合の媒体としては下記の3つがよく使われます。
Youtube広告
WEBCM動画の活用方法として最も一般的な媒体がYoutubeです。日本だけでも6500万人以上のユーザーを抱えており、またYoutube自体が「動画視聴」を目的とした媒体であることからも動画広告との相性は他の媒体と比較して良いと言えます。

Facebook広告・Instagram広告
FacebookおよびInstagramは、動画広告の配信先としてYouTubeに次ぐ代表的な媒体です。中でもFacebook系のプラットフォームは、ターゲティング精度の高さに強みがあり、広告主が届けたい層へより的確にリーチできる設計になっています。
InstagramはMeta社(旧Facebook)が運営しており、広告の配信システムや設定項目はFacebookと共通です。つまり、どちらを選んでも同様のターゲティング条件を設定できます。
特にFacebookは、ユーザーのプロフィール情報や行動データが非常に豊富で、たとえば「学歴」「誕生日」「居住エリア」や「位置情報」に基づいた絞り込みが可能です。こうした細かな条件設定により、年齢層・関心領域・生活圏に応じた配信戦略が立てやすくなります。
たとえば、
- ビジネス系サービス:都市部に住む30〜40代の会社員に向けてFacebook広告で展開
- 美容やダイエット商材:Instagramを使う20〜30代の感度が高い層を狙う といった具合に、商材の性質に応じて最適な媒体を選択することがポイントです。
また近年では、Facebook・Instagramともに広告配信におけるAIの最適化技術が進化しています。性別や年齢といった基本的な条件だけを設定し、詳細な絞り込みはAIに任せた方が成果が出やすいケースも増えています。広告設計の柔軟性と運用効率を両立できる点も、大きな魅力です。
X(旧Twitter)
Xを活用した動画広告の大きな特長は、「拡散のスピード感」と「反応のしやすさ」にあります。
まず拡散性の高さについて。Xはリツイートや引用リツイートといった機能を通じて、元の投稿がフォロワーのフォロワーまで届く仕組みが整っています。実際、話題となるコンテンツの多くがこの仕組みを通じて急速に広まり、「バズ」や「炎上」といった現象が起こる場としても知られています。広告が自走的に広がっていく構造は、他のSNSにはない強みと言えるでしょう。
さらに注目すべきは、ユーザーが反応しやすい環境設計です。特に「いいね」の操作に対する心理的ハードルが低く、Instagramのようなビジュアル重視のSNSに見られる「これは本当に評価するに値するか?」といった文化がXにはあまり存在しません。“気軽にいいねを押せる”文化が根づいているため、投稿への反応が得られやすく、そこからの二次拡散にもつながりやすくなっています。
このように、Xでは「簡単なアクションが大きな広がりに直結する」という構造があるため、拡散力と即時性を重視する動画広告との相性が非常に高いといえます。
制作費別の動画事例
どれくらいの予算で、どんなサービス紹介動画が制作できるのか…?というのは気になりますよね。
サービス紹介動画は自前で用意できる環境や人員(見栄えのする撮影場所や、お話が得意な人)によって大きくクオリティが変動するので、一概に「この金額があればこのクオリティが実現できる!」というのは難しいのですが、参考値として、30万円・60-80万円・100-150万円・200万円以上でどんなサービス紹介動画が制作できるのかをピックアップしてみました。
30万円
30万円というのは、制作会社に依頼する際の最低限の金額です。そのため、イラストやデザインを書き起こして制作するというのは難しく、購入素材を組み合わせて動かす形で制作する、もしくは素材自体を発注側から提供することが前提になると考えておくとよいでしょう。
60-80万円
50−60万円ほどの予算があると、ある程度は素材を制作会社側で用意する、書き起こした上で動画制作を行うことができます。
100-150万円
100-150万円ほどの予算が用意できると、しっかりとデザイン・イラスト素材を書き起こしで制作し、アニメーションさせることが可能になります。自社サービスのコンセプトやブランドイメージを動画でしっかりと表現することを考えると、これくらいの予算を確保したいところです。
200万円以上
200万円以上の予算になると、格段にクオリティが上がります。
・デザイン、イラスト素材制作時のコンセプト策定
・コンセプトに沿ったデザイン、イラスト制作
などに始まり、アニメーション・動かしのレベルとしてもかなり高いものになってきます。
サービス紹介動画の制作のポイント
サービス紹介動画の制作において、特に気をつけなければならないのは下記の4点です。
- 目的を明確にする
- 役割を明確にする
- ターゲットを明確にする
- 明確なコール・トゥ・アクションを設定する
具体的にどのようなポイントを抑えるべきか、1つずつ解説します。
目的を明確にする
すごく当たり前のことなのですが、意外と見落とされがちです。
「なんとなくカッコいい動画」「とりあえずサービスの内容を理解してもらえるような動画」とかだと、あまり意味のない動画が出来上がってしまいます。本当にもったいないです。
ちなみに、ここでいう「目的」は「LPの滞在時間を伸ばす」とか「CVを上げる」とかだと動画クリエイティブに落とし込むには少し抽象的です。
しっかりと役割を果たすことが期待できる動画を制作するためには、上記の「目的」に2〜3回ほど「WHY」をぶつけてみて下さい。
- なぜ滞在時間が短いのか?→欲しい情報がない?誤った流入のさせ方をしている?
- CVがあがらないのか?→そもそも今が上限?最後の一押しができてない?
という感じで、ある程度のところまで深ぼったり要素分解しながら「動画の目的」を明確にしましょう。
役割を明確にする
このポイントは先ほどの目的よりも見落とされがちです。目的が定まればそのための動画制作!となりそうですが、それでは上手くいきません。動画は魔法のツールではないので、動画を制作・活用しただけで目的が達成されるということはありません。
先ほどの通り、目的が「LPの滞在時間を伸ばす」だとして、そのために動画はどのような役割を果たすべきなのか。
- 「LPで伝えている情報を補足する」ことで理解を促すのか
- LPの内容を「ファーストビューでハイライト的に伝える」ことで以降の内容に興味を持ってもらうのか
- 「ユーザーの声を説得力高く伝える」ことで信頼してもらうのか
…など、「LPの滞在時間を伸ばす」ことを目的だとしてもできることはたくさんあります。
つまり、動画制作の目的はもちろん、動画の役割まで決めることで、初めて「どのような動画を制作するべきなのか」が決まると言えます。
ターゲットを明確にする
すごくすごく当たり前のことですが、これも見落とされがち…というか動画を制作するにあたっては少し解像度が荒い状態であることが多いです。
例えば、LPのターゲットは「パーソナルトレーニングに興味のある20−40代の男女」だとして、動画のターゲットもそのままでよいのか?もう少し絞ったほうがいいのか?あるいは、広げたほうがいいのか?という部分を検討しきれていないケースがあります。
- ターゲットは「パーソナルトレーニングに興味のある20−40代の男女」
- 動画を制作するのは、〇〇〇〇という目的で、動画には〇〇〇〇という役割を担わせたい。
- そうすると、動画のターゲットは「パーソナルトレーニングに興味のある20−40代の男女」かつ「どちらかというと、〇〇〇〇タイプ」というように絞り込まれるのか「運動経験のない人も含める」というように少し広げるのか。
…という感じです。
明確なコール・トゥ・アクションを設定する
「行動喚起」と訳され、デジタルマーケティングの世界ではユーザーに「次に起こしてほしい行動」を誘導することを指します。
つまり、動画を視聴したあとの行動としてどのような行動を期待するのか、そしてそのためにどのような気持ち・感情になって貰う必要があるのかを明確にしましょう、ということです。
当然ですが、やはりこの点についても目的との紐づきがあり、目的の解像度が低いとターゲットやコール・トゥ・アクションも同じように解像度が低い可能性が高いです。
もし、動画制作を具体的に検討しているようでしたら、まずはこれらのポイントを整理することから始めてみましょう。
お問い合わせ前に準備しておきたいこと
制作をご検討中の方には、以下のポイントを整理した上でご相談いただくと、よりスムーズに進行できます。
- 動画の目的(理解促進/広告/コンセプトなど)
- 想定されるターゲット
- 使用媒体(Web、SNS、イベントなど)
事前の情報整理から、しっかりとサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にお声がけください。
情報整理や予算の検討などの事前準備がご不安な方は筆者がお手伝いいたします。
是非、下のボタンからお気軽にお問い合わせください。